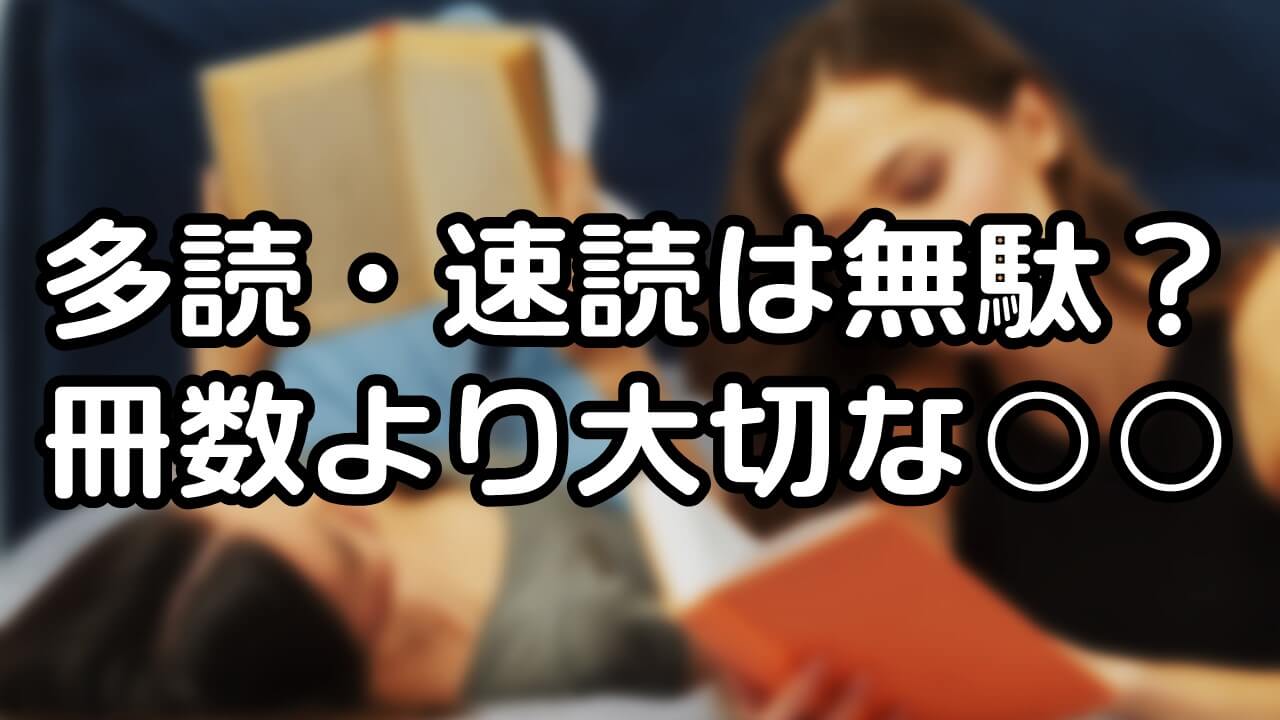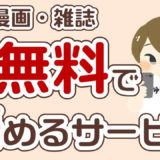多読とか速読って、「凄い感」がめちゃくちゃありますよね。
- 僕、1ヵ月で30冊読むんですヨ~
- 本1冊30分で読み終わりまスー!
- 年間100冊読む僕がおすすめ!
なんか、それだけで「この人頭良さそう」「なんか凄そう」な感じが漂ってますが、大量に読むこと・早く読めること自体に価値ってないですからね。
極論、1冊でOK
というのが僕の考えなので、それについて書いていきたいと思います。
大前提として、読書方法なんて人それぞれです。
あと、ここで言う「本」は小説や娯楽のために読む本ではなく、
- 仕事に活かす
- 知識を深める
などを目的とした読書を指しています。
目次
多読・速読は無駄?

多読・速読(本をたくさん読むこと)はもちろん無駄じゃないです。
僕なりにメリット・デメリットをまとめてみますね。
多読・速読のメリット
- 幅広い知識が身につく
- 自分の興味ある分野or興味ない分野が明確になる(自己分析)
- 本屋に行ったときに表紙やタイトルを見て中身を想像することができる(複眼的視点)
想像に難くないよう、多読・速読のメリットはこんなところですかね。
知識が身につくことはもちろん、たくさんの本を読むことで自分の興味を知ることができます。
作家・エッセイストの山口瞳さんはこんな言葉を残しています(戸田智弘 著『学び続ける理由』より)。
読書法は、ただひとつ、濫読せよという説があり、私もこの説に大賛成である。
特に若いうちは絶対に濫読が必要である。
濫読の時期のなかった人は大成しないと極言してもいい。
 ゆうすけ
ゆうすけ
そして、最後の「本の中身を想像できる」というのが結構大きなメリットだったりします。
どういうことかというと、、、僕らって当然、すべての本を読むことはできませんよね。
ちなみに、1日に約200冊もの本が出版されていると言われています。
つまり、「何かを読む」ということは即ち「何かを読まない」ということでもあるんです。
その中で、今の自分にはどんな本をが必要か?を考えて読む必要があり、多読はその直観力を鍛えてくれます。
 ゆうすけ
ゆうすけ
この視点は、本を選ぶ際に非常に役に立ちます。
このメリットについて気づかせてくれた、こちらの本を紹介しておきます。
多読・速読のデメリット
- 読んだ内容を忘れたときマジデ時間の無駄
- たくさん読めるということは難解な本を読んでいない証拠
あまり多読・速読のデメリットについて触れられていない気がするので、強調して言いたいのですが…
この2つのデメリット、まじで大事です
勝手な偏見かもしれませんが、読んだ「だけ」で満足してる人がいる気がするんですよね…
話題のビジネス書を読んでだけで、「他の奴等を一歩出し抜いちゃってるぜオレ♪」みたいな(マジデ勝手な想像ですが、実際過去の僕はこんなんでした)。
ビジネス書なら特にですがその本で得た知識…
使わないと意味ないから!!
そして内容を忘れたらもっと意味ないから!!
なんか読んだことに満足してる人っていませんか?
勉強として、学びとして本を読むのであれば読書って「手段」ですよね。
 ゆうすけ
ゆうすけ
あと、これは本の読み方によりますが、「大量に読める=簡単な本しか読んでない」ってことに繋がります。
「本」って一言にいっても、30分で読めてしまうような中身が薄い本から、1週間かけても読み解くのが難しい重厚な本まで様々です。
当然、「難しい本を読んでるから偉い」なんて言いたいわけではありませんが、本当に読書を通して成長したいのであれば、難しい本にも挑戦していくべきです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
例えばですが、2024年から一万円札の顔となる渋沢栄一は孔子の『論語』を何度も読み返したそうです。
論語と言うと、紀元前500年に生きた中国の思想家である孔子の教えが書かれた書物なので、理解するのは激ムズなわけです。
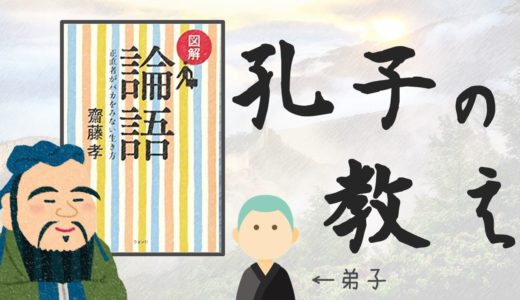 【書評】論語の名言まとめ→孔子の教えをわかりやすく図解で解説|仕事・人間関係・学び・生き方のキホン
【書評】論語の名言まとめ→孔子の教えをわかりやすく図解で解説|仕事・人間関係・学び・生き方のキホン 読むのが簡単、ということはつまり、自分の知っていることが多く書かれてるってことです。
自分の知っていることばかり読むのか、自分が理解できないけど、それを何周もして嚙み砕いて自分の中に落とし込むのか、どちらが本当に自分のためになるかは明白でしょう。
極論1冊でいい理由

僕は読む本の冊数は極論1冊でいいと思っています。
例えば、「仕事術」を謳うビジネス書は世の中に山のようにありますよね。
本屋さんで「これよさそうだなー」と思った本を買って、そこに書いてあることを1年間通して実践していったら、きっと他の人を出し抜いて「仕事ができる奴」になれますよね。
だって、本を読む人は世の中の一部、そしてそれを読んで実践する人なんて、さらにその中の一部ですから。
かく言う僕は割と本を読みますが、最近は自己啓発とかビジネス書は一切読みません。
 ゆうすけ
ゆうすけ
この本は僕の愛読書で何度も読み返して実践に移しています。
この本、読めば読むほど、新しい発見のあるスルメ本。ひとつひとつのエピソードを水野敬也さんは細かくこだわって書いたんだろうなって思ってます。
僕は「この本に書いてあること、すべて自分の中に吸収できた!」と思えるくらい、自分のものとしない限り、他の仕事術とかの本は読まないだろうなって思ってます。
こういったベストセラーになっている本をいくつか読めば、おそらく自分に合った本が見つかると思うので、その1冊に出会えたらその本を大切にしましょう。
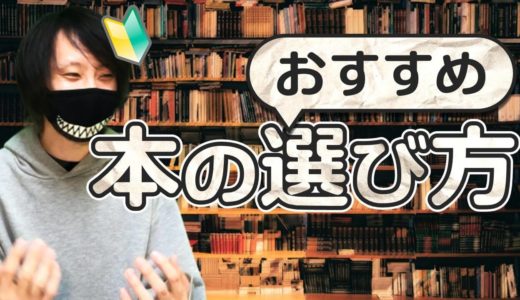 読書に慣れてない人は何から読めばいい?本の選び方とおすすめ本3冊を紹介
読書に慣れてない人は何から読めばいい?本の選び方とおすすめ本3冊を紹介 本の選び方で迷ったらこちらの記事を参考にしてみてください。僕の考えをまとめました。
大事なのは読む「目的」

ここで言う読書は娯楽としてではなく、勉強のため、成長のための読書を指しています。
そのときの「目的」って当然、たくさん読むことではないですよね。
- 自分を成長させるために本を読むなら、目的は読んで得た知識を使って、行動に移して自分に変化を与えること
- 歴史を勉強するために本を読むなら、目的は歴史を頭に入れること、もしくは入れた知識を使うこと
本を読むことは手段なんです(当たり前)。
これ(手段の目的化)、マジデ世の中のありとあらゆることに共通して陥りがちなミスです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
ビジネスマナーって仕事を円滑に進めるためのものですよね…??
- 目的:仕事を円滑に進める
- 手段:ビジネスマナー
なのに、新人研修では決められたマナー(名刺交換の仕方とか…)を教科書通りに教わったと思ったら、仕事では全く使われていないという….。
 ゆうすけ
ゆうすけ
ってなりました。苦笑
要はみんな、マナーを教えることが目的になって、本来の目的を見失っちゃってるなーって思いました。
だって仕事が円滑に進められるのであればそれでいいんだから「敬語だと堅くて、やりにくいからラフに話しましょう!」と仕事相手に言われたら、敬語なんていらんわけです。
読書に関して言うと、「読んだ冊数=その人の読書家ぐあい」みたいにわかりやすい指標で測られるので、こういったミスに陥りやすいですね。
「1年で365冊を達成するために、今日は3冊も読んだ!」みたいなツイートをしている人を見ると「oh…」と思っちゃいます。
速読本が溢れてる理由を考えてみよう
最後に、、、速読本っていつも本屋で平積みされている気がしませんか?
実際、Amazonで「速読」と調べると関連書籍が山のようにできてきます。
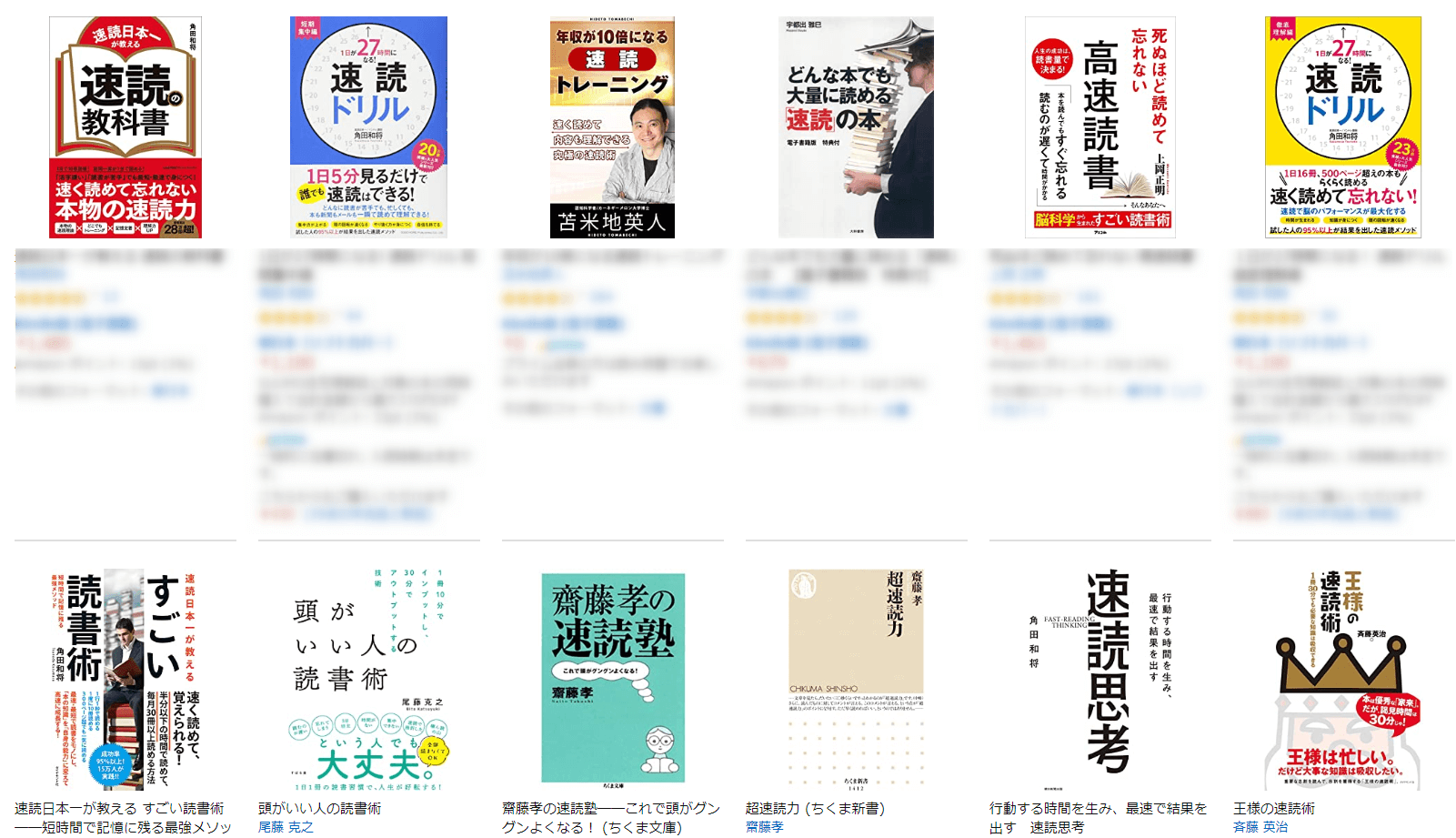
Amazonの検索結果
速読本が発売され続けるのって、「速読ができるようになりたい…でもできない!」という人がたくさんいる証拠です。
 ゆうすけ
ゆうすけ
あ、あと、「本はたくさん読んだ方がいい!」という多読・速読のメリットを訴えることで、本の売上に繋げようという魂胆もあるんじゃないかとも少し思ってます。
ってな感じで、周りに流されず自分のスタイルで本を読んで欲しいですね。
ということを踏まえて、、、たくさん読むことはもちろん無駄じゃないけど、そんな難しいこと(速読)に挑戦するより、1冊じっくり読むことをおすすめします~。ではっ!!