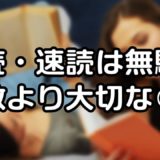二宮金次郎の石像って小学校に必ず置いてますよね?僕が通っていた学校にはいました。
「薪を背負って本読んでるから、学問の神様なのかなぁー」なんて子供ながらに思っていましたが、調べてみると彼は…
農業の発展につくした偉人
でした。

本記事は、こちらの『世界の伝記 二宮金次郎』(監修 東京大学前教授・文学博士 笠原一男さん)をもとに作成しています。
目次
二宮金次郎って何をした人?
二宮金次郎の功績を大きく分けると3つあります。
学問を農業に活かし二宮家を立て直す

二宮金次郎は貧しい家庭に生まれ、金次郎が13歳の時に父親を亡くし、15歳の時に母親を亡くすという、決して恵まれたとは言えない環境で育ちました。
当時、江戸時代は、火山の噴火により火山灰が土地を覆い飢饉がおこったり、大雨によって川が洪水し畑が台無しになる、ということがある、そんな時代です。
 ゆうすけ
ゆうすけ
金次郎は父(利右衛門)の兄(万兵衛)の家にひきとられます。
当時、農民にとってお米をどれだけ多く耕すことができるのか?が大きな課題でした。
お米は自分たちが食べる分はもちろん、幕府に年貢として納める分、何か非常事態が起きたときの蓄えとして必要だったからです。
そこで金次郎は、父の影響(父は学問を好み家には本がたくさんあった)もあり、学問の重要性に気がつきます。

金次郎は本で学んだことを、農業に活かし、多くのお米を耕すことに成功し、次々と田んぼを開墾していきました。
自分一人で十分なお米を作ることができるようになった金次郎は、万兵衛の家をでて独立することとなります。
そして金次郎は村でも指おりの地主となり、使用人をつかうほどとなり、見事に二宮家の立て直しに成功したのです。
恵まれない環境にいながらも、学問を農業に活かすことで二宮家を復活させた。
当時の価値観を現代に当てはめると、「多くのお米を耕すことができる=お金持ち」くらい、農民にとってお米は貴重なものだった。
大名の財政を立て直す

1812年(文化9年)、金次郎は小田原藩の家老(大名の家来の中で一番上の役人)服部十郎兵衛の屋敷に住み込んで働くことになります。
そこで金次郎が目にしたのは、屋敷に住む人たちの粗末な生活っぷりでした。
- 高級品を買う
- 明かりの無駄遣い
- ご飯の食べ残し
案の定、大名の財政はどんどん苦しくなり、多くの借金を抱える事態となりました。
農民の金次郎は、表面では派手に見える大名の、お金の無駄遣いを見て、「このままでは農民がいくら年貢を納めたところで無駄だ」ということに気がつきます。
そして金次郎は、服部家(大名)から財政の立て直しを頼まれます。
そこで、金次郎はたった5年で立て直すことを約束するのと同時に、屋敷の行動の一切をすべて金次郎に任せることを約束します。
その約束というのは・・・
- 食事はだれも飯と汁にかぎること
- 着物は絹はやめ、安くてじょうぶな木綿にすること
- むだな遊びごとはいっさいしないこと
といった地道な努力を積み重ねるものでした。
 ゆうすけ
ゆうすけ
そして5年で財政を立て直すという約束を果たし、借金を全部返済し、さらには余剰のお金も残すほどの結果を残しました。
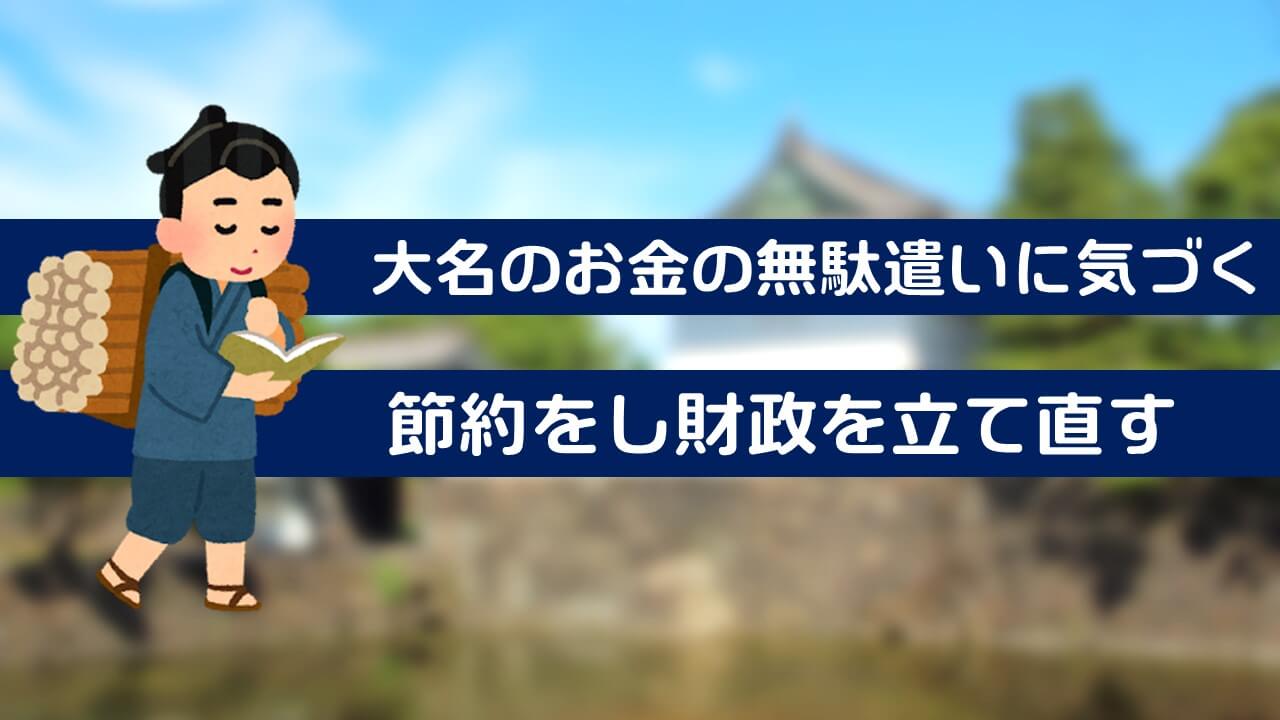
農民の年貢の納め先である、大名の服部家には多くの借金があり、このままではダメなことに気づく。
そして農業で成り上がった経験をもとに、服部家の借金を返し財政の立て直しに成功した。
廃れた町を農業の力で立て直す

金次郎の噂はみるみる広まり、小田原藩の城主である大久保忠真(おおくぼただざね)の耳にも届き、忠真から町の立て直しを頼まれます。
その町というのが、桜町領です。
桜町は、今の栃木県二宮町。
桜町領では計算では米4000俵がとれるとされていたが、土地が痩せていて3000俵がやっとの状態で、大勢の農民が土地をすてて逃げ出していました。
残った農民も働く気がないなど廃れた町となっていました。
藩主(大久保忠真)からの頼みというのは、目もくらむような名誉なことでしたが、金次郎は桜町領の立て直しの難しさを知っていました。
金次郎は町の農民に、ただ節約をすすめるだけでなく、働く気持ちを起させるような方法を取り入れていきました。
ただ、こうした金次郎の活躍をおもしろく思わない役人たちもいたのです。
そのため金次郎の計画を邪魔されることもありましたが、金次郎の勤勉さと指導の的確さが、町の人たちから評価され、慕われるようになります。

金次郎は上手くいかないときに、行いを改めるために21日間の断食修行をし、断食がおわったばかりというのに、80kmあまりの道を歩いて桜町まで帰ったという逸話があります。
そして桜町の人々は、金次郎を中心にして力を合わせ、1894俵ものお米を年貢として納めるほどになりました。
その活躍が噂され、金次郎はその後も鳥山藩(栃木県)、下館藩(茨城県)、相馬藩(福島県)などの立て直しを手がけ、たくさんの農民を救うこととなります。
状況が酷く、立て直しが難しいと言われた桜町領の立て直しに成功。
その後も、多くの藩の立て直しに寄与する。
二宮金次郎の基本プロフィールと年表

基本プロフィール
- 名前:二宮金次郎(二宮尊徳)
- 生没:1787-1856年(69歳)
- 出身:神奈川県の農家
- 身長:182cmあったとされる
※二宮金次郎は町の人から尊敬され、二宮尊徳先生(にのみやそんとく先生)または(たかのり)と呼ばれるようになりました。
年表
- 1787年:父(利右衛門)、母(よし)の長男として生まれる
- 1800年(13歳):父が病死
- 1802年(15歳):母が病死
- 1804年(17歳):万兵衛の家を出て独立
- 1818年(31歳):服部家の立て直しを任せられる
- 1831年(44歳):桜町領の立て直し成功
- 1856年(69歳):「墓石を立てるな。土をもり上げて松か杉を一本植えておけばよい。」という遺言を残して亡くなる
二宮金次郎の格言
二宮金次郎が大切にしている考えを格言を通して紹介します。
積小為大
小を積んで大を為す
これは、小さなことを積み重ねてはじめて、大きなことができる、という意味です。
金次郎は、本を読むために必要な明かりをつけるために、油が必要でした。
そのときに金次郎は何をしたかと言うと、
- 一握りの油菜の種を借りる
- 荒れ地に種を撒く
- 次の年に油菜が花を咲かせる
- 借りた油菜を売る
- 余分に獲れた油菜の種を油に変えた
というステップを踏み、油を確保し、その明かりで学問をしたということです。
本を読み、学んだことを農業に活かし、多くのお米を耕すという大きなことを為すために、油菜を地道に育てるという小さなことを積み重ねたわけです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
道徳と経済
道徳なき経済は犯罪であり
経済なき道徳は寝言である
金次郎の父は、人に親切にする人で、貧しい人たちにお米やお金を分けてあげるような人格の人でした。
ただそうしているうちに、いつのまにか蓄えがなくなっていき、さらには貸したお金を返してもらえないこともありました(父は「栢山(地名)のお人好し」とからかわれていたそう)。
それで苦しい思いをした金次郎だからこその言葉です。
 ゆうすけ
ゆうすけ
商売の心得
すべての商売は
売りて喜び
買いて喜ぶようにすべし
これは、商売は、買った人が喜ぶようにしろ、ということです。
お金を貸したり、借りたりするときも、両者が喜ぶようにしなければならないということです。
当たり前のことですが時には、商売をする際は、自分のことを考えて利益だけを追い求めてしまうよね。
 ゆうすけ
ゆうすけ
おまけ話
偉人の話を聞くと、「すごい才能だな・・・」と感想を抱くことはありますが、僕は二宮金次郎のその勤勉さに凄く感銘を受けました。
お米を多く獲るために地道に勉強し、財政を立て直すために節約したというのは、まさに「小を積んで大を為す」を体現したことだと思います。
よく「日本人は勤勉だ」と海外から日本を見たときに言われることですが、二宮金次郎の功績はまさに日本人の強さを表した生き様ですよね。
二宮金次郎は、初なすを食べて、その年の凶作を予想できたそうです。
これは二宮金次郎の舌が肥えているというより、それだけ農業に向き合い努力したからこそ、なすを通して土質の変化に気づけたからです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
単行本: 144ページ
監修の言葉
二宮金次郎は、お金にこまっている藩や、生活に苦しんでいる農村のたてなおしをした指導者としてゆうめいです。
金次郎は江戸時代のおわりころ、神奈川県の農家に生まれました。
はやくに父母に死にわかれた金次郎は、苦労しながら農業について勉強をしました。
そして人手にわたった生家を復興したことがみとめられ、小田原藩の財政や、農村のたてなおしに力をつくしました。
こちらの学習漫画『世界の伝記シリーズ』は、子供だけでなく大人でも楽しく偉人を通して歴史を学ぶことができるのでおすすめ。
もっと詳しく知りたい人はぜひ読んでみてくださいっ♪