野口英世は貧しい農家に生まれ、幼い頃に左手が不自由になるほどのやけどをするなど苦労をしましたが、大変な努力をして明治という時代に世界的な医者となりました。
南米には英世を称えた「ヒデヨ・ノグチ小学校」という名前の学校があるほど。日本では千円札紙幣の肖像画となっていますよね。

ウィキペディアより
人々がいかに英世に感謝したかがわかります。本記事では、野口英世の功績や名言をわかりやすく解説していきます(下記書籍を参照しています)。
目次
野口英世の功績とは?
野口英世の功績で有名なのは黄熱病の研究ですが、それだけではありません。数が多いので時系列順に紹介していきます。
中国でペストの治療をする
1898年、英世は北里柴三郎が所長を務める伝染病研究所の助手として雇われていました。
北里 柴三郎(1853年-1931年)は、日本の医学者・細菌学者・教育者・実業家。
「日本の細菌学の父」として知られ、ペスト菌を発見し、また破傷風の治療法を開発するなど感染症医学の発展に貢献した。

ウィキペディア参照
そこで北里柴三郎から、横浜の検疫医官補になるよう助言を受けます。
伝染病が入ってくるのを防ぐために、港で外国から入ってくる人や品物を調べる人のこと。
そこで英世はふたりのペスト患者を発見しました。
ねずみなどのノミからうつる死ぬ割合の高い伝染病。
この仕事ぶりが認められ、英世は清(中国)の牛荘へ日本人医師たちと一緒に行くことになります。
ペストに苦しむ中国の人たちを助けるためです。
英世は中国へ渡る船の中で、中国語を覚えてしまったという逸話があります。
英世は中国へ着くとすぐに診療を始め、ペストに苦しむ中国人を助けました。
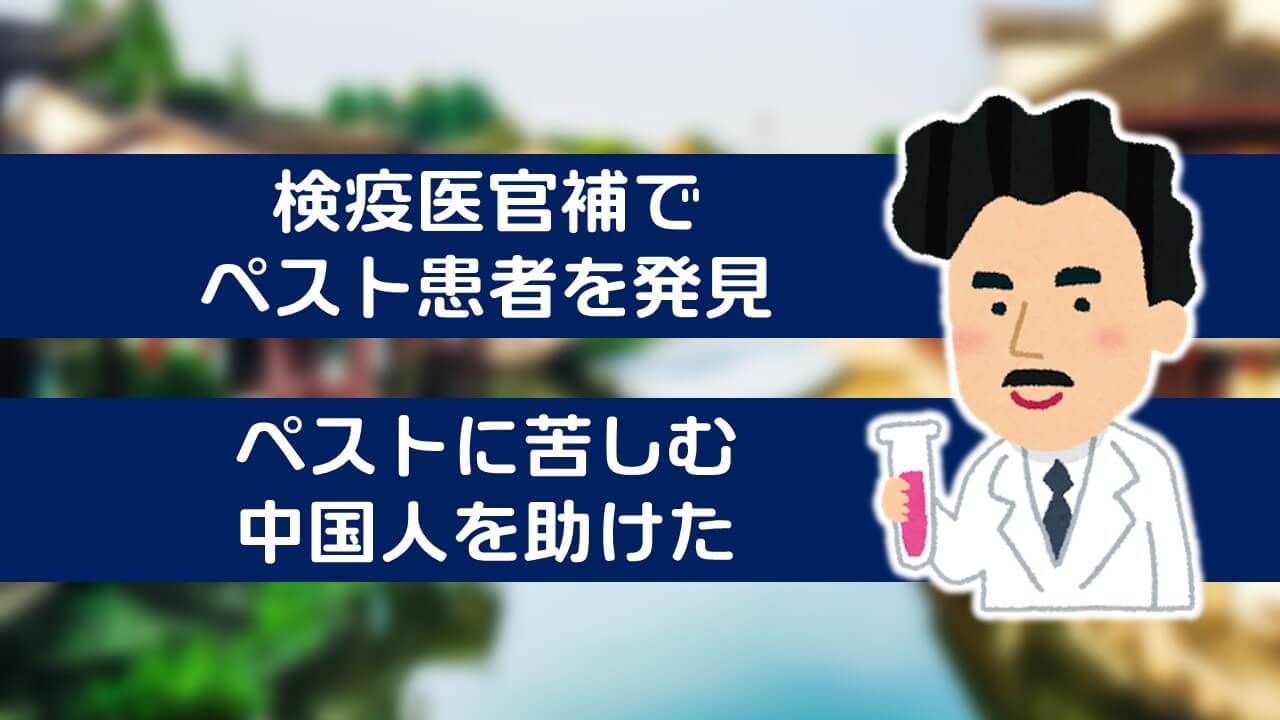
アメリカで蛇の毒の研究
1900年、英世はアメリカのサンフランシスコに着きました。
ペンシルベニア大学のフレクスナー教授のもとで働くためです。
そこでフレクスナー教授から「蛇の毒の研究で人手が足りない」と言われ、蛇の毒の研究をすることになります。
蛇のことなど何も知らない英世でしたが、図書館に通い蛇の毒についての研究論文を読みました(発表された世界中の蛇の毒に関する論文をすべて読んだと言われる)。
英世が蛇の毒の研究を初めて三ヵ月後、本や実験でまとめた蛇の毒に関するレポートをフレクスナー教授に提出します。
その功績が認められ、蛇の毒の研究が英世とフレクスナー教授とミッチル博士との共同研究として、フィラデルフィアの学会で、英世によって発表されました。
そのあくる年の1902年の秋、英世はペンシルベニア大学の病理学助手になりました。
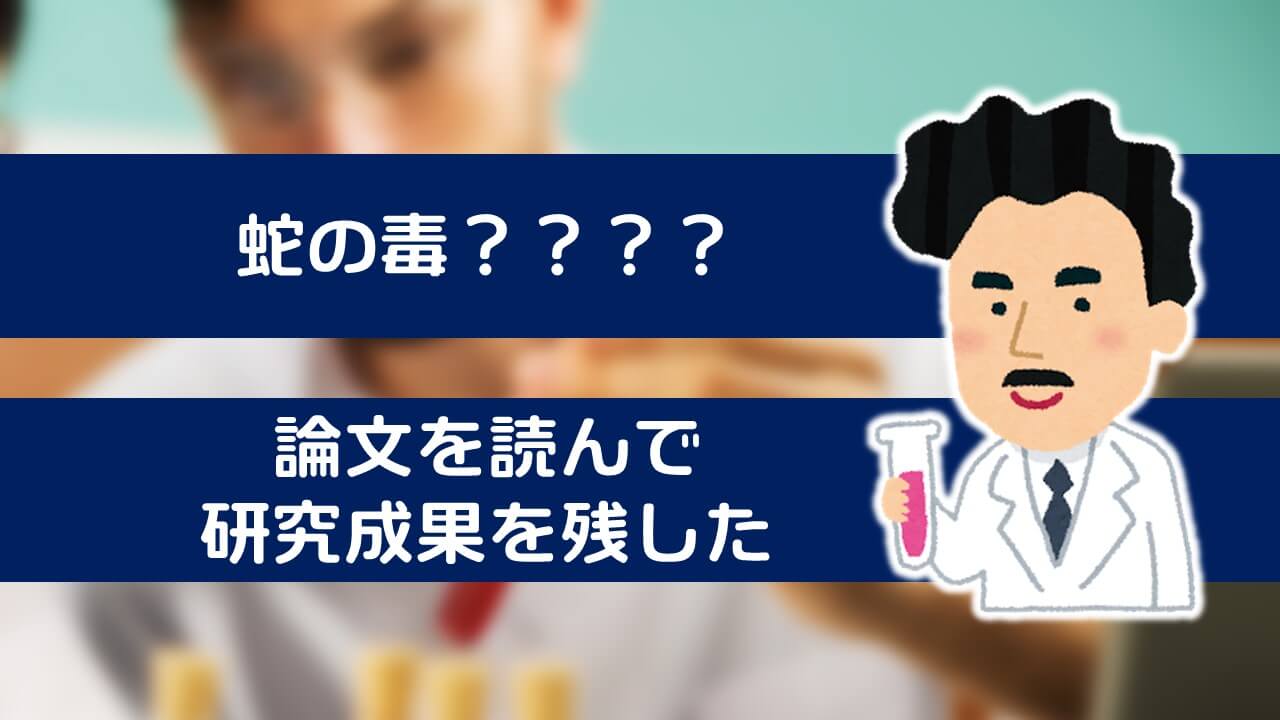
スピロヘータの純粋培養に成功
ヨーロッパにわたった英世はデンマークの国立血清研究所に入り、研究を続けました。
そこで英世は研究所所長のマドセン博士のもとで、血清学の研究をしました。
血清とは、血液の中の成分のひとつ。
この成分に毒などに打ち勝つ力を持たせる研究のことを血清学という。
ヨーロッパでの留学を終えて、アメリカに帰ってきた英世はロックフェラー医学研究所(恩師のフレクスナー教授が所長、当時最も進んだ研究をしている施設)に入りました。
この研究所で、英世は梅毒(伝染病)のもとになるスピロヘータという最近の研究をしました。
スピロヘータの純粋培養に成功すれば、研究に役立つのですが、この頃はまだだれも成功していませんでした。
1911年、英世はスピロヘータの純粋培養に成功し、この研究は世界中に認められることとなります。
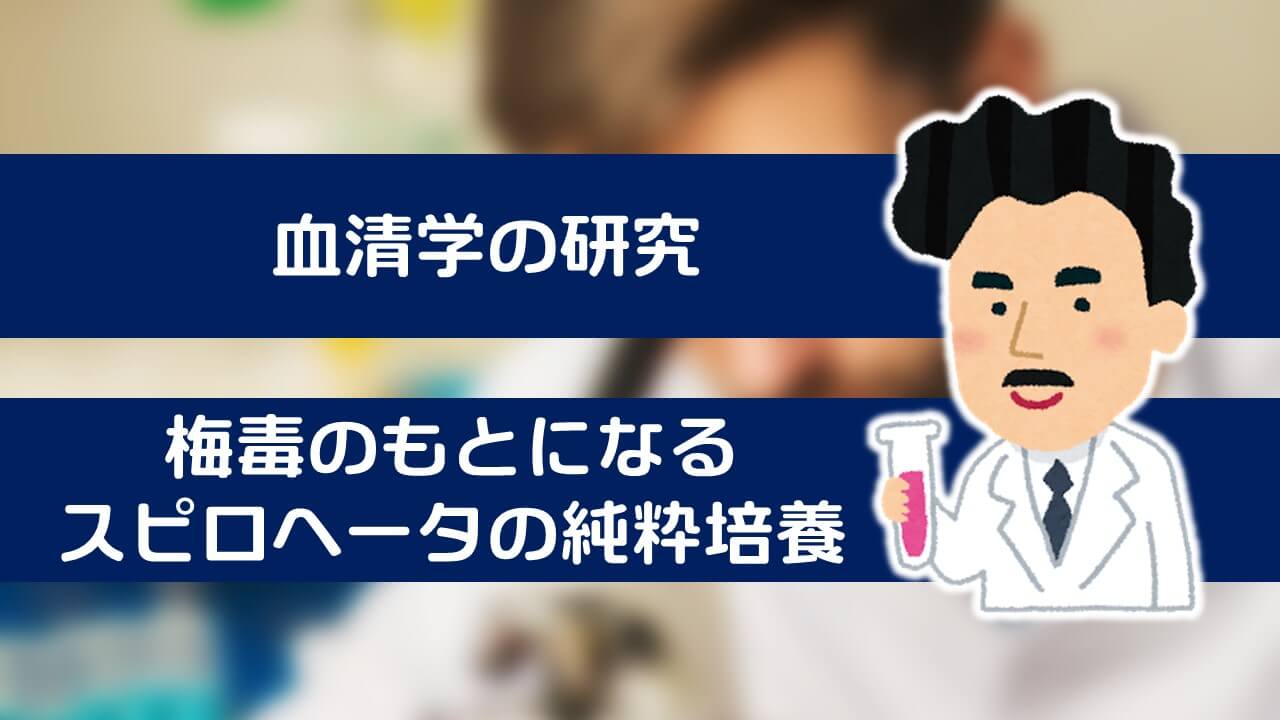
黄熱病の研究
1918年、英世は南アメリカで流行している黄熱病の正体を調べるためにエクアドルに行きました。
かかると40度の熱がでて、体の皮膚が黄色くなる伝染病
英世は誰も発見できなかった黄熱病の病原体をたった9日間で見つけだしました(後に黄熱病の正体を捉えられていなかったことを知る)。
ただ、このおかげでワクチンを使って、エクアドルの国の黄熱病は治まりました。
このとき英世に勲章や名誉教授の称号まで送られ、また、町の通りの名前にノグチ通りと付けたりと、英世への感謝を表しました。
しかし1924年、ジャマイカのキングストンで開かれた会議で、英世の発見した病原体は黄熱病のものとは違う、と指摘を受けました。
英世が発見した病原体は、黄熱病と同じように高い熱が出て、皮膚が黄色くなるワイル氏病という菌の一種だったと考えられています。
1927年、英世はアフリカのガーナへ旅立ち、イギリス政府が建てた研究所でヤング所長と一緒に、黄熱病の研究を始めました。
ところが英世自身が、黄熱病にかかってしまい、1928年、5月21日に英世(58歳)は息をひきとりました。
のちに、黄熱病の病原体をロックフェラー研究所の人によって発見されました。そしてそれは、電子顕微鏡のなかった英世の時代には、とうてい発見できないものだったのです。
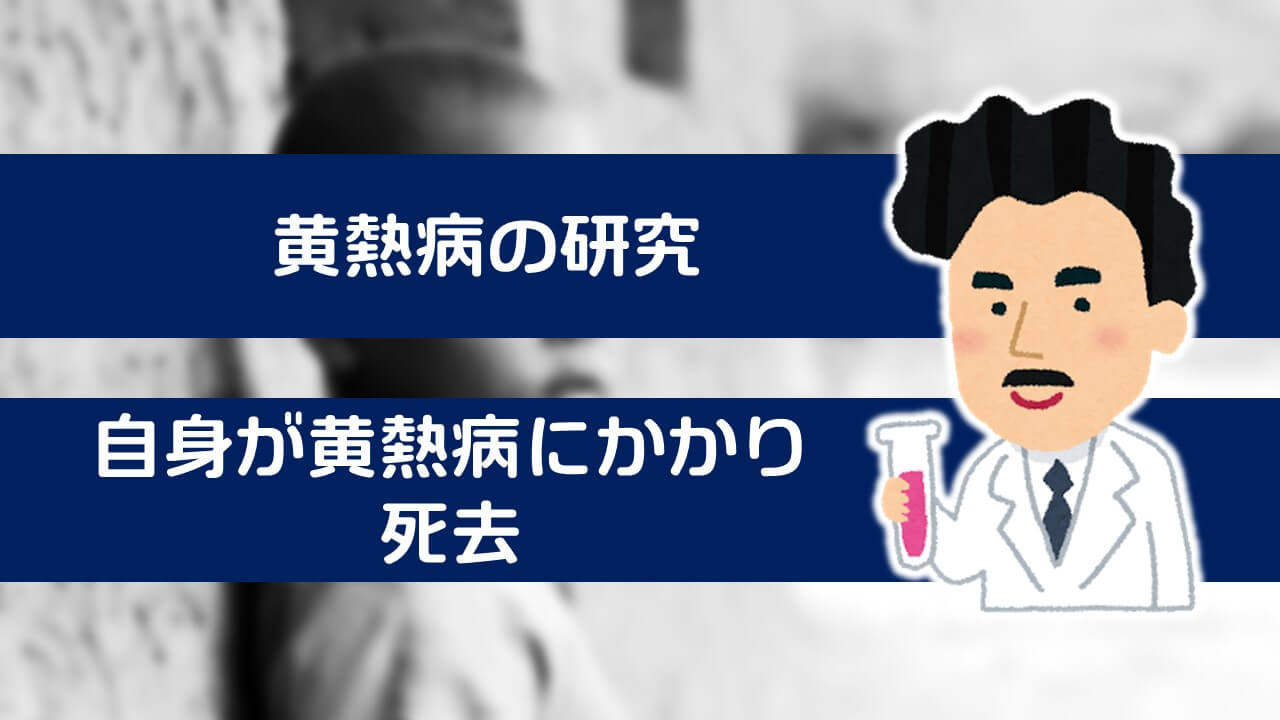
野口英世の名言を紹介
名言1
志を得ざれば再び此の地を踏まず。
英世は20歳のとき、医者になるために東京へ行くことになります。
そのとき、実家の柱に刻んだ言葉がこの「志を得ざれば再び此の地を踏まず。」です。
これは、自分の目的をはたせないならば、二度とここにはもどらないという意味です。
 ゆうすけ
ゆうすけ
名言2
誰よりも三倍、四倍、五倍勉強する者、それが天才だ。
野口英世ってめちゃくちゃ努力家なんですよね。
ロックフェラー研究所の人からは「日本人は寝ないのか!?」と驚かれるほどの働きっぷりだそうです。
ナポレオンは夜三時間しか眠らなかった。彼になし得られる努力が、自分になし得られぬはずがない。
『日本の偉人100』p125より
 ゆうすけ
ゆうすけ
名言3
モノマネから出発して、独創にまでのびていくのが、我々日本人のすぐれた性質であり、たくましい能力でもあるのです。
英世は「世界のヒデヨ・ノグチ」と呼ばれるほど名声を得たあと、日本の医学博士の学位が送られたときに、たいそう喜んだそうです。
世界で活躍しても、日本に住む母に喜んでくれることを望んだのです。
そこから愛国心が伺えるうえ、日本人の強さを世界にアピールしたのでした。
「真似るのが上手い」と言われる日本人の気質ですが、独創にまで伸ばせるというのが、日本人の素晴らしいところだということを知っていたのです。
野口英世の基本プロフィールと年表
基本プロフィール
- 本名:野口清作
- 生没:1876-1928年(51歳)
- 出身:福島県耶麻郡猪苗代町
野口英世は、生まれの名は清作と言い、「英世」という名前は、幼いころからお世話になっていた小林先生から命名された名前です。
ちなみに、なぜ清作の名前を変えたかと言うと、坪内逍遥の「当世書生気質」という本にでてくる登場人物「野々口清作」と被ったからと言われています。
登場人物「野々口清作」はみんなから期待されながら、酒に溺れてダメな人間になってしまったのです。
年表
- 1876年:生まれる
- 1896年:医者になるため上京
- 1896年:(北里)伝染病研究所の助手になる
- 1899年:清の牛荘に行く
- 1901年:フレクスナー博士の助手になり蛇の毒の研究をする
- 1911年:梅毒スピロヘータの純粋培養に成功
- 1918年:エクアドルで黄熱病(正確にはワイル氏病と言われる)の病原体を発見
- 1927年:ガーナで黄熱病の研究・死去(墓地はニューヨーク)
英世の遺体はニューヨーク市北部の郊外ウッドローンの墓地に埋められました。
英世の墓には「野口英世、彼はそのすべてを科学にささげ、すべてを人々のために生き、すべての人のために死んだ」と刻まれています。
野口英世の有名な失敗談
最後に、英世の有名な失敗談を2つ紹介します。
左手をやけど
英世が幼い頃に、左手が不自由になるほどのやけどを負ったことは有名です。
左手が棒のようになっていることから、「てんぼう」というあだ名がつけられ、いじめられた子でした。
もともと英世は勉強があまりできない子でしたが、そのくやしさをバネに勉強を頑張ったんですね。
当時は小学校を出ると、お金持ちしか勉強できなかったのですが、勤勉さが認められ高等小学校へ進むことができたのです。
そして、英世の努力をみた先生や生徒がお金を出し合って、左手を手術し、完璧にではありませんが、手を動かせるようになりました。
 ゆうすけ
ゆうすけ
血脇守之助の援助金を使い果たした
フレクスナー教授が来日して、英世が案内役を務めたときに、アメリカに留学し医学の勉強を志します。
しかし、アメリカに渡るのには大金が必要です。
そこで、血脇守之助が英世の勉強ぶりに感心し、渡米費用の300円を英世に援助金として渡します。
血脇 守之助(ちわき もりのすけ、1870年3月2日(明治3年2月1日)- 1947年(昭和22年)2月24日)は、日本の歯科医師。
東京歯科大学の創立者の一人。明治後期から昭和初期にかけて日本の近代歯科医療制度の確立に尽力した。

ウィキペディアより
がしかし!
アメリカ行きを祝福した送別会で、英世は血脇先生から貰った援助金をすべて使ってしまったんです。苦笑
 ゆうすけ
ゆうすけ
もちろん血脇先生は激おこでしたが、英世の才能と努力を信頼し、最後まで援助を続けました。
英世含むこういった偉人の失敗談が面白くまとめられたコチラの本、おすすめです。
最後に
本記事は主に『学習漫画 世界の伝記 野口英世』を参考に書きました。
学習漫画シリーズは子供向け書籍かもしれませんが、大人の僕が読んでもとても面白かったです。
正直僕は、野口英世が千円札の肖像画になる理由は、この本を読むまで全く知りませんでした。
が、英世がどれだけ医学に功績を残したのか、どれだけ多くの人を救ったのかを、表面的に知ることができました。
僕は小学生ながらに「伝染病の研究をしたのがどこが凄いの?」なんて思っていましたが、いま2020年5月、伝染病の怖さを全世界の人々が思い知らされていますよね。
「野口英世のような偉人が、この令和の時代に生きていたら・・・」そんなことを感じてしまいます。






