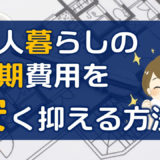偉人の人生や教訓からは学ぶべきものが多くあります。
世界の偉人というと、スティーブジョブズ、エジソン、アインシュタイン、ニュートン、ガリレオ、、、
日本の偉人というと、聖徳太子、徳川家康、野口英世、福沢諭吉、、、
もう数えたらキリがないくらいいますよね。
今回は、僕が読んだ「偉人」に関するおすすめ本を全部で8冊紹介したいと思います。
目次
偉人の人生や考え方がわかるおすすめ本
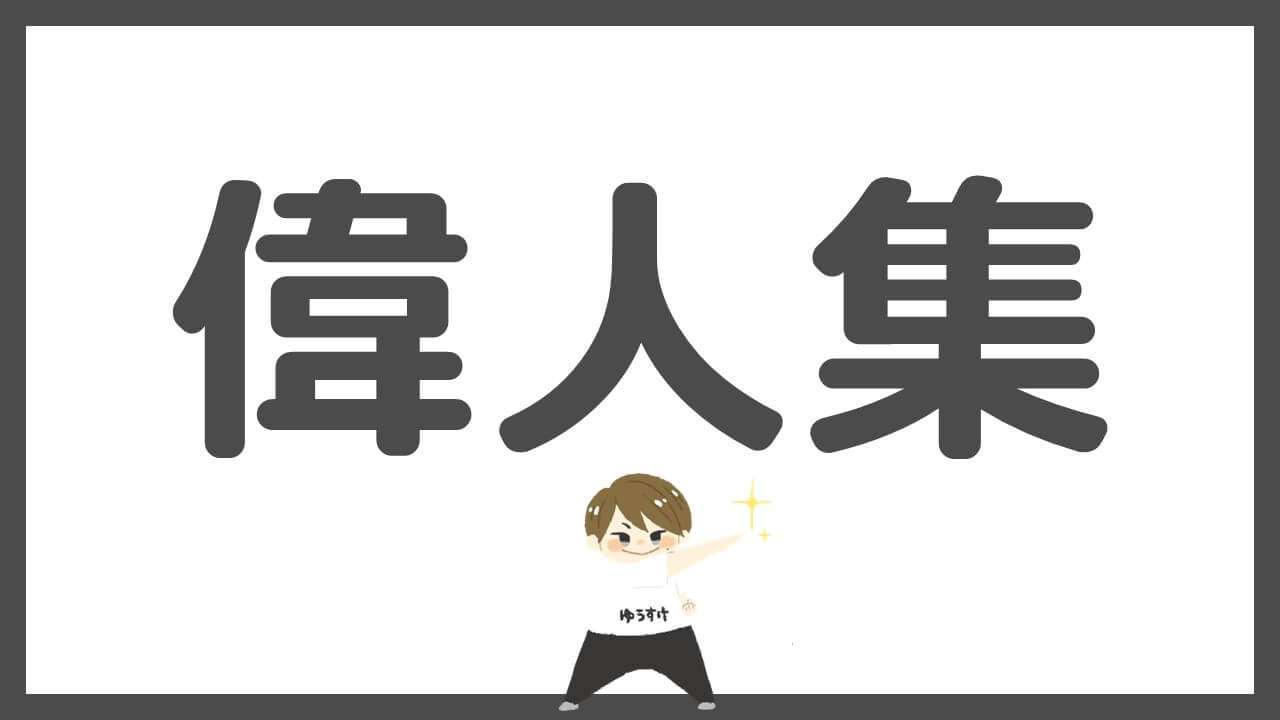
偉人のことをおおまかに、わかりやすく知れるおすすめ本を紹介します。以下3冊は小学生でも読めるような簡単な内容になっています。
学習漫画シリーズ
学習漫画シリーズは図書館などで見たことがある人も多いと思いますが、大人が読んでも全然楽しめます。
「学生のとき歴史を学ぶのが苦手だった」という人におすすめしたいですね(実際ぼくがそうだったので..)。
特に、世界の伝記シリーズは大好きです。
僕は「日本人ならまずは、日本の偉人について知ろう」と思って、
- 野口英世
- 徳川家康
- 一休さん
- 福沢諭吉
- 二宮金次郎
- 新渡戸稲造
この6巻セットを買って読んでみましたが、どれも面白かったです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
この国には昔、こんなにも素晴らしい人物がいたんだと、日本に生まれたことを誇りに思えるほどです。
漫画とは言え、専門家の方が監修の本なので、その偉人を知るには十分足りるような内容になっています。
個人的におすすめなのは、野口英世のストーリーです。バカみたいな感想ですが、「英世はんぱねぇ」って読みながら何度も思いましたね。
どっかのドラマの主人公かな?と思えるくらいの活躍っぷり。
 ゆうすけ
ゆうすけ
失敗図鑑
偉人を語る本にしては少しイレギュラーかもしれませんが、この本も個人的には超おすすめ。
偉人と言うと、必然的に、その人の「成功ストーリー」にフォーカスして解説されますよね。
ただ、偉人って、めちゃくちゃに成功してる陰で、めちゃくちゃに失敗してるんです。笑
本書は、成功ではなく、「失敗ストーリー」にフォーカスした本で、偉人の新たな側面が見れて結構おもしろいので、YouTubeなんかでもよく紹介されています。

iPhoneを生み出したAppleの創業者であるスティーブジョブズの失敗談は、有名ではありますが、僕はこの本を通じて知りました。
しかもこの本が面白いのが、本の体裁がけっこうヤンチャなところです。笑
何を言ってるのかわからないかもしれませんが、表紙に描かれてるようにイラストたっぷりで、遊び心のある体裁になっています(読みたい人はぜひ買ってね!)。
天才たちの人生図鑑
紀元前から二十世紀後半まで、100人の偉人がピックアップされた本です。
メインは見開きで1人の人物に対して、格言と500字程度の説明が書かれており、タイトルに「人生図鑑」とある通り、その偉人の一生をざっくり知ることができます。
なので、「この偉人について詳しく知りたい!」というより「有名どころの偉人がどんな人生だったのか概要を知りたい」という人におすすめ。
イラストもたっぷりでフルカラーなので読んでいても全然飽きません。
「おもしれぇ!」とはなりづらいと思いますが、「このくらいは知っておかないとネ」といった教養が身につくので、どちらかと言うと大人におすすめかなーと。
個人的に知って欲しい偉人
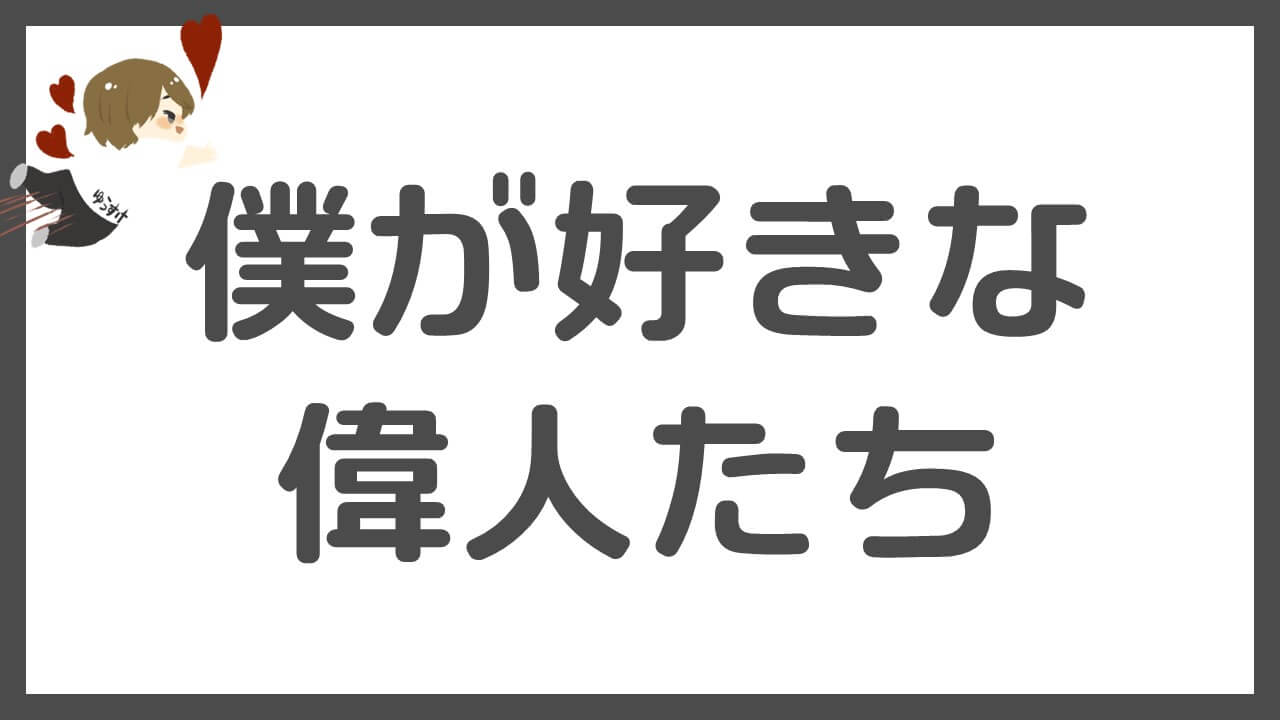
ここからは僕の独断と偏見で、「この偉人のことは知って欲しい!」という偉人にフォーカスした関連書籍を紹介します。
僕が読んだことがある本を並べているだけなので、他の書籍でも自分に合ったものを選ぶといいと思います。
孔子(論語)
紀元前552年または紀元前551年‐紀元前479年
春秋時代の中国の思想家、哲学者。儒家の始祖。
釈迦、キリスト、ソクラテスと並び四聖人(四聖)に数えられる。
その死後約四百年かけて弟子達が編纂したのが『論語』である。
ウィキペディアより
ぜひとも知って欲しいのが孔子の教えです。
理由はシンプルで、四聖人と数えられている人の中で、最も教えがわかりやすいからです。
例えば…
これを知る者は、これを好む者に如かず。
これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。
これは学ぶことにおいて、「楽しむことが一番」ということで、言うなれば「好きこそものの上手なれ」ということです。
紀元前から言い伝えられている人としての「道理」を教えてくれます。
新しい発見はないかもしれませんが「やっぱ大事だよなぁ」としみじみと感じさせてくれます。
聖徳太子
574年2月7日-622年4月8日
飛鳥時代の皇族・政治家。
推古天皇のもと、蘇我馬子と協力して政治を行い、国際的緊張のなかで遣隋使を派遣するなど進んでいる中国の文化・制度を学び冠位十二階や十七条憲法を定めるなど大王(天皇)や王族を中心とした中央集権国家体制の確立を図った他、仏教や儒教を取り入れ神道とともに信仰し興隆につとめたとされる。
ウィキペディアより
「聖徳太子」だけにフォーカスした本は読んだことがないので、関連記事を載せておきますっ。
 【3分で解説】聖徳太子って何をした人?わかりやすく解説【仏教・憲法・遣隋使】
【3分で解説】聖徳太子って何をした人?わかりやすく解説【仏教・憲法・遣隋使】 日本史を語る上で、彼は外せないでしょう。
- 仏教を導入
- (日本で初めて)憲法を制定
- (日本で初めて)位の制度を導入
- 遣隋使の派遣
このあたりは日本人として知っておくべき知識かと思っています。
”聖徳太子は10名の意見を同時に聞き分けることができた”みたいな都市伝説って聞いたことありますよね?
このワードだけが独り歩きしてる感じはありますが、これは「それだけ多くの人に対して的確な教えを説くことができた」ことからそう言われているだけです。
つまり、それだけ頭の切れる人物であったと言うことです。このあたりちょっと詳しくなるだけで凄く面白いですよ!
他には聖徳太子が日本のことを「日いづる国(太陽が昇る国)」と表現したエピソードが好きですね~。
 ゆうすけ
ゆうすけ
福沢諭吉(学問のすすめ)
天保5年12月12日〈1835年1月10日〉 – 明治34年〈1901年〉2月3日
日本の武士、蘭学者、著述家、啓蒙思想家、教育者。
慶應義塾(旧:蘭学塾、現在の慶應義塾大学はじめ系列校)の創設者であり、商法講習所(のちの一橋大学)、神戸商業講習所(のちの神戸商業高校)、北里柴三郎の伝染病研究所(現:東京大学医科学研究所)、土筆ヶ岡養生園(現:東京大学医科学研究所附属病院)の創設にも尽力した。
ウェキペディアより
江戸時代の鎖国政策をやめ、日本が現代のようなグローバルな国となるにあたって活躍した人物。
西洋の進んだ文明を日本に持ち込むことで、日本は急速な近代化を図ることができました。
僕らがパンを食べたり、洋服を着たりと、今となっては当たり前になっている洋風文化はここから始まったのだと、知ることができます。
福沢諭吉の一生が知りたい人は、こちらの学習漫画がおすすめ。
福沢諭吉の一番有名な著書『学問のすすめ』には何が書かれているのか?をわかりやすく知りたい人はこちらの斎藤孝さんの本がおすすめです。
「学ぶことがいかに大切か?」の根底がわかると思います。
渋沢栄一(論語と算盤)
天保11年2月13日(1840年3月16日) – 昭和6年(1931年)11月11日
日本の武士、官僚、実業家、慈善家。
ウィキペディアより
2024年度から新しく一万円札の肖像画となることが発表され、多くの人に認知されたと思います。
彼は「近代日本の資本主義の父」と呼ばれるほど、日本の経済活動に大きく寄与した人物です。
渋沢栄一は「論語」を熟読するほど、孔子の道徳観に惹かれたそうです。
そしてその「道徳と経済の両立が大切である」という主張(これを道徳経済合一説と呼ぶ)が書かれたのが『論語と算盤(そろばん)』です。
正直、僕は読んでいてもつまらなかったし、教訓を得ることはできませんでしたが、これだけの偉人の言葉に触れておくことが大切かと思ったので、ここで紹介しました。
野口英世
1876年(明治9年)11月9日 – 1928年(昭和3年)5月21日
日本の医師、細菌学者。
主に細菌学の研究に従事し、黄熱病や梅毒の研究で知られる。数々の論文を発表し、ノーベル生理学・医学賞の授賞候補に三度名前が挙がったが、黄熱病の研究中に自身も罹患し、1928年(昭和3年)5月21日、英領ゴールド・コースト(現在のガーナ共和国)のアクラで51歳で死去。
ウィキペディアより
才能と努力の天才すぎてビビった人物です。笑
野口英世は伝染病の研究に貢献した人物で、僕が英世に関する本を読んでいた頃、ちょうど新型コ○ナウイルスが世界中で流行っているときでした。
 ゆうすけ
ゆうすけ
ページをめくる度に英世の偉人エピソードが詰まっているのがこちらの学習漫画。イチオシの偉人です。
最後に
偉人について知るのって「考え方がタメになる」とか「人生の軌跡が教訓になる」みたいなメリットもありますが、僕はシンプルに楽しいから勉強しているところが大きいです。
「事実は小説よりも奇なり」なんて言いますが、偉人の人生なんてまさに「奇なり」のオンパレードですもん。
あと、自分の人生のスケールの小ささに気づかされます..。
紹介した『失敗図鑑』とか読んでるとみんなド派手にやらかしてますからね。笑
自分の小さな失敗なんて屁でもないなーなんて思えたりして、よりフットワーク軽く物事に挑戦できる気がします。
偉人の人生はリアルだからこそ面白い!!