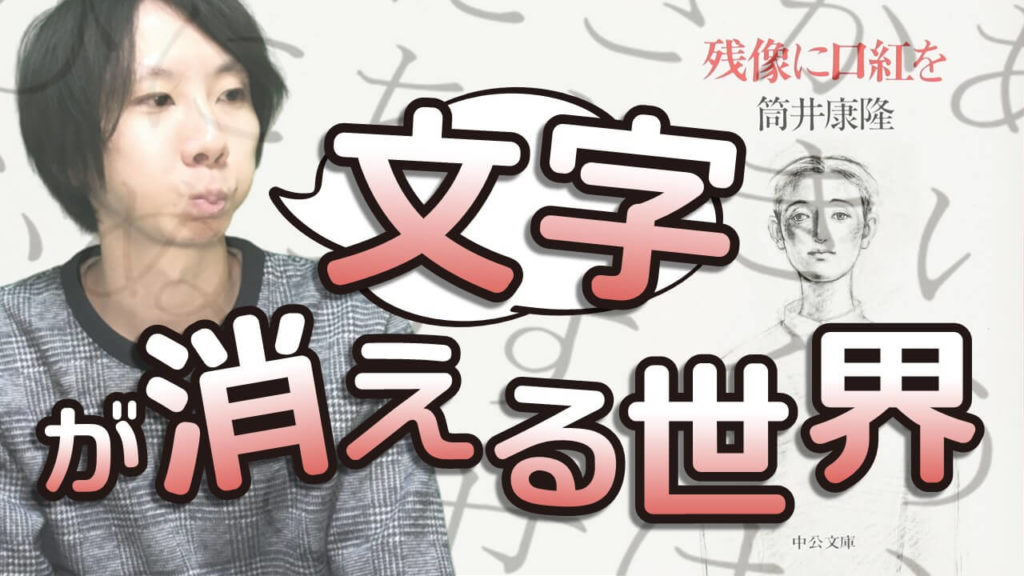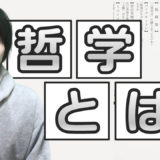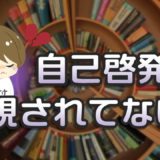ゆうすけ
ゆうすけ
今回はSF御三家と称される作家のひとり筒井康隆さんの『残像に口紅を』という小説を読んだのでネタバレなしのあらすじと感想を書いていこうと思います。
- 著者:筒井康隆(1934年-)
- 出版:1995年(中公文庫)
- 337ページ
目次
あらすじ
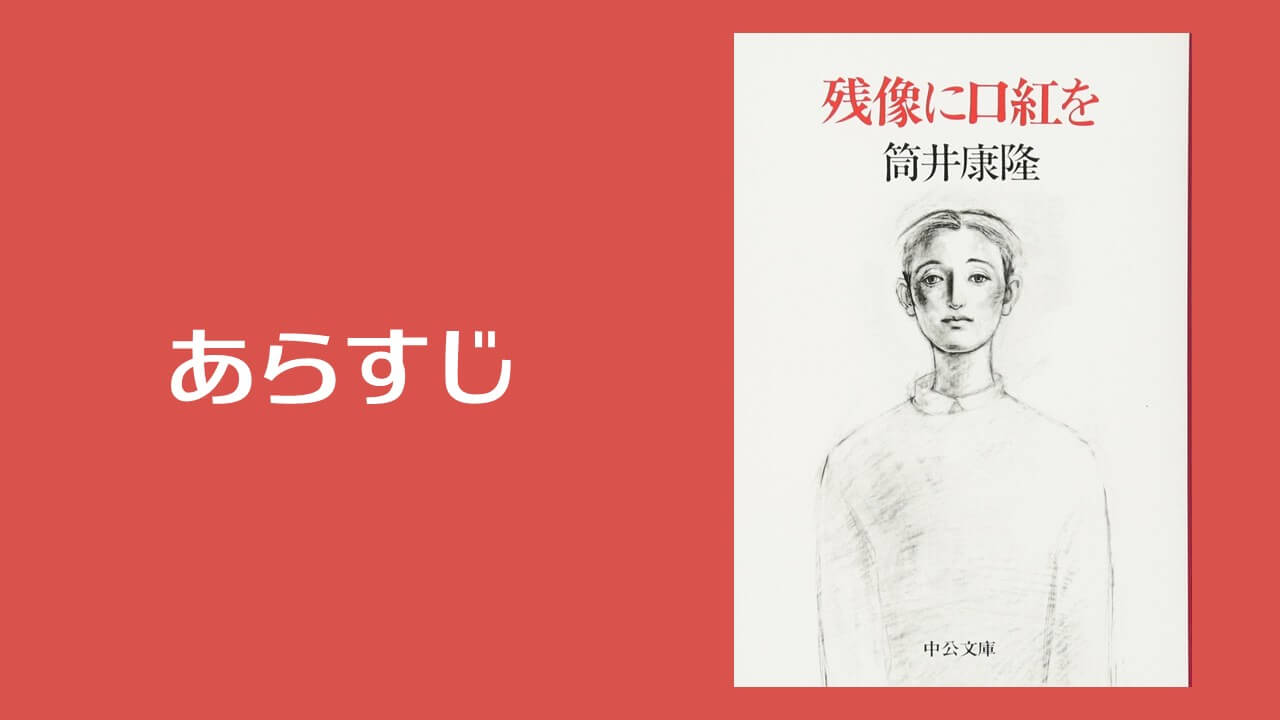
「あ」が使えなくなると、「愛」も「あなた」も消えてしまった。
世界からひとつ、またひとつと、ことばが消えてゆく。
愛するものを失うことは、とても哀しい…。
言語が消滅するなかで、執筆し、飲食し、講演し、交情する小説家を描き、その後の著者自身の断筆状況を予感させる、究極の実験的長篇小説。
Amazon説明文
世界から一文字ずつ、文字が消えていき、さらにそれを表す言葉もなくなっていく。
そんな世界を、文字だけで構成される小説でいかに表現するのか?
このような実験的な試みからこの小説は「実験的長編小説」と呼ばれています。
 ゆうすけ
ゆうすけ
話の内容は、なんてことのないある作家が主人公の日常を切り取ったものです。
ですが、この物語の不思議なところが…
主人公自信が、この「世界から文字が消えていく」という虚構の設定を作り出し、その中で生きているということです。
不思議な設定の国があって、そこに主人公がポンっと放り込まれるわけではなく、この設定の物語(虚構)を主人公自身が作り上げているということです。
だから、主人公の考えが小説内でこのように書かれていたりします。
そういえばこの虚構にはまったく事件が起こらないな。読者が退屈しないように、何か事件を起した方がいいのだろうか。
感想
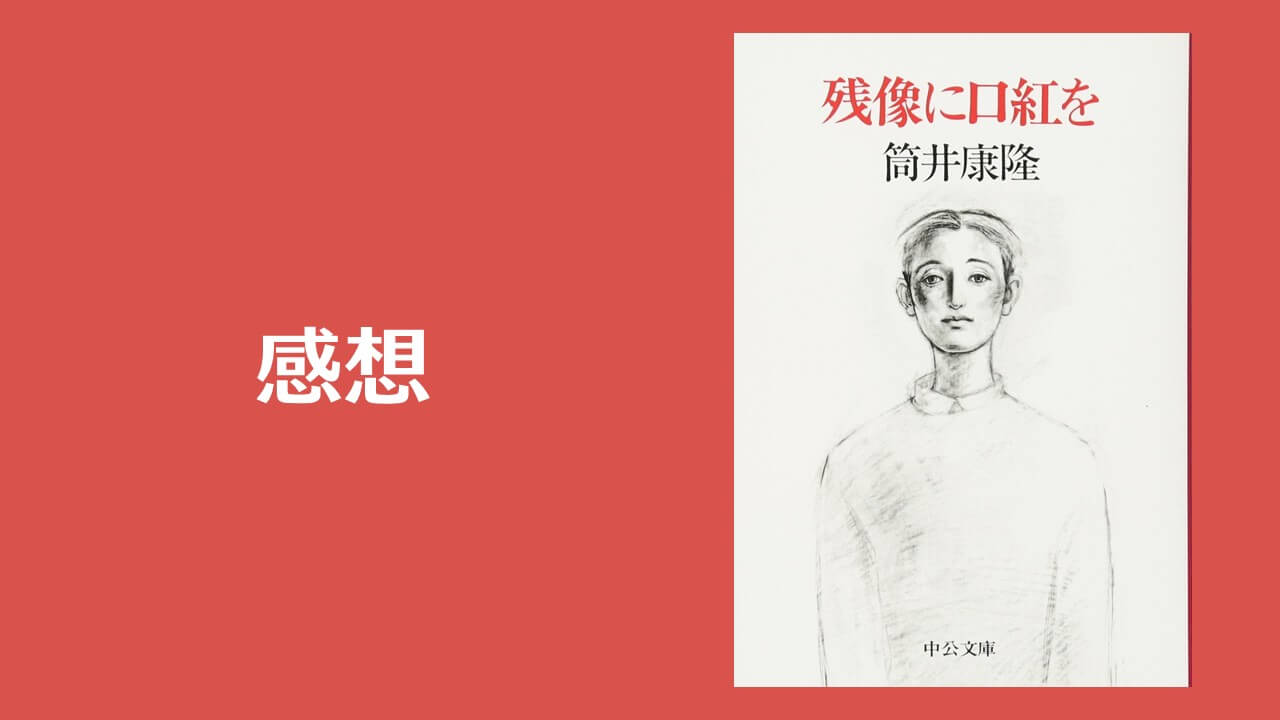
物語とかストーリー自体の正直な感想は「ぶっちゃけあまり面白くなかったな…」です。
 ゆうすけ
ゆうすけ
「文字が消えていく」という設定を活かしたストーリー展開とも思えなかったし、終わり方もぶっちゃけナンダカヨクワカラナイ。そんな感じでした。
 ゆうすけ
ゆうすけ
ただ、小説は基本、文字しか使わないのにも関わらず、その文字をどんどん消していく、という「発想」や、「小説ならではの世界観の作り方」は、面白いなと思いました。
「小説ならではの世界観の作り方」というのは例えば、「し・ん・ぞ・う」のどれかの文字がなくなったとしたら、死んでしまうのか?という問いに対して
君は小説を書いている時、いちいち『彼は胸部左側に心臓をひとつ持っていて』などという人物紹介をやるかい。
表現上どうしても必要になった時以外は、虚構内存在としての君や僕には心臓は、または心臓ということばは不必要なんだ。
あくまでも小説という虚構を成り立たせるために必要な文字が消えていく、ということなんですね。
このあたりの、「小説が成り立っていることのリアル」と「文字が消えていくという虚構」が入り混じる不思議な作品でした。
小説という虚構の中で…
- 文字がなくなっていくと、世界はどう変化するのか?
- 文字がないなかで、どうやって出来事を表現するのか?
ストーリー性重視というよりは、実験的要素が強い小説だと感じました。
 ゆうすけ
ゆうすけ
何より筒井康隆さんすげぇ
このような面白い試みも着眼点のひとつですが、何より凄いのが、このめちゃくちゃな設定を成り立たせてしまう、著者の力です。
- 文字がなくなっていくというのを醸し出して読者を楽しませつつ
- 普通に小説として違和感なく文章が成り立っている
この二つを両立させているのが、作家の表現力の多さを物語っているなと思いました。
最後の方になってくると、さすがに苦しまぎれの表現がでてきて、しかも、いちいち回りくどい表現をしないといけないことに対するやりづらさが漏れていてそこも面白い。
 ゆうすけ
ゆうすけ
おまけ話
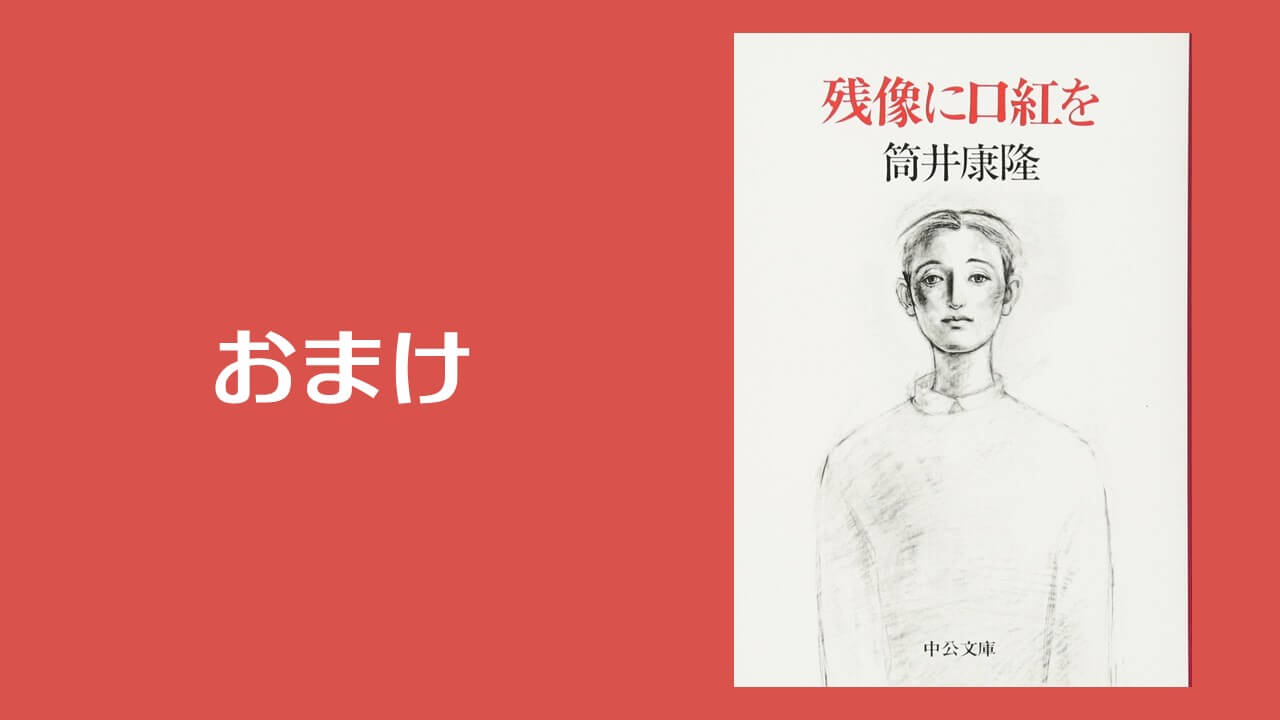
物語の後半になってくると、登場人物のうちで「何か言いたいんだけど、それを表す言葉が消えてしまって、話そうにも話せない」という人がでてきます。
主人公は作家さんだから、ボキャブラリーが豊富なんですね。
そこでちょっとイジワルしてわざと「答えられないだろうな」、という質問をしてみて、その人がしどろもどろになっているのを見て、優越感に浸るシーンがあります。
博識な著名人が、無知な人を論破するアレにみえて、現実と重なる部分があると思いましたとさ。