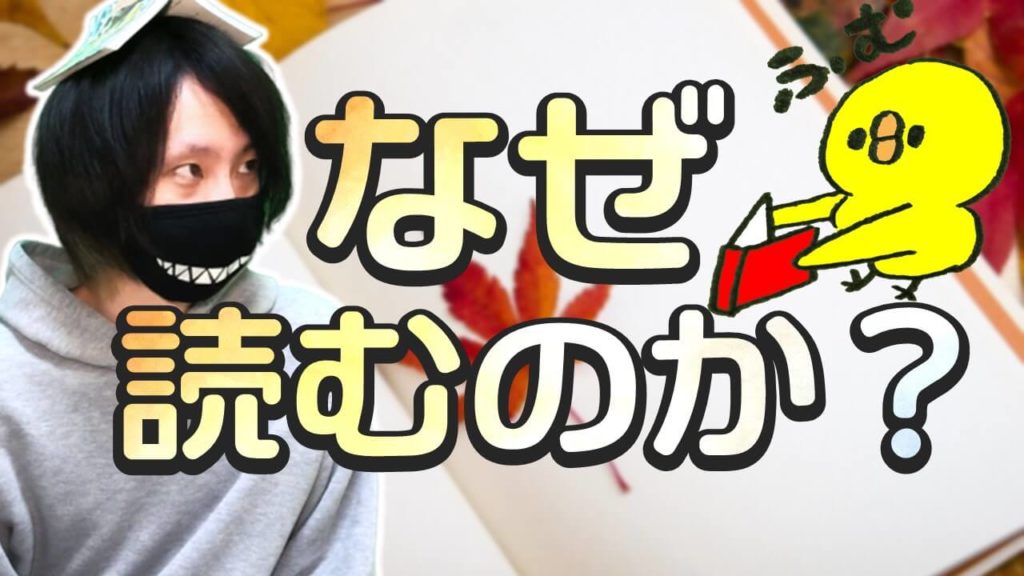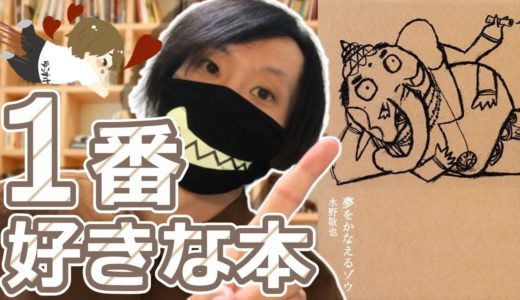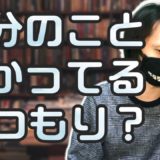\動画で見たい方/
どうも、キャッチーに言うために年間100冊読んでいると言いつつ、実際どれくらい読んでいるのか把握してない、ゆうすけです。
今回は本の紹介ではなく、僕が考える「いまこの時代に読書をするべき理由」について、主観たっぷりで書いていこうと思います。
 ゆうすけ
ゆうすけ
目次
動画ではなく本で勉強する理由
先に大雑把に結論を言ってしまうと、「読書の方が勉強になる」から。だから読書の方が楽しい。
 ゆうすけ
ゆうすけ
知らないことを知る作業って、人間に備わっている知的好奇心がくすぐられる楽しい作業です。
それをたった1000円程で教えてくれる本の存在はやっぱり偉大です。
 ゆうすけ
ゆうすけ
本作りに携わる方全般(著者・編集者・表紙デザイナー)ほんと凄いなと思うのが、本屋に行って30分くらいプラプラしたら、大体10冊くらい読みたくなる本に出会うことができます。
「100冊持って帰っていいよー」って言われたら、苦もなく喜んで選ぶことができるんですよね。それくらい本って知的好奇心をくすぐってくれます。
理由1:楽じゃない
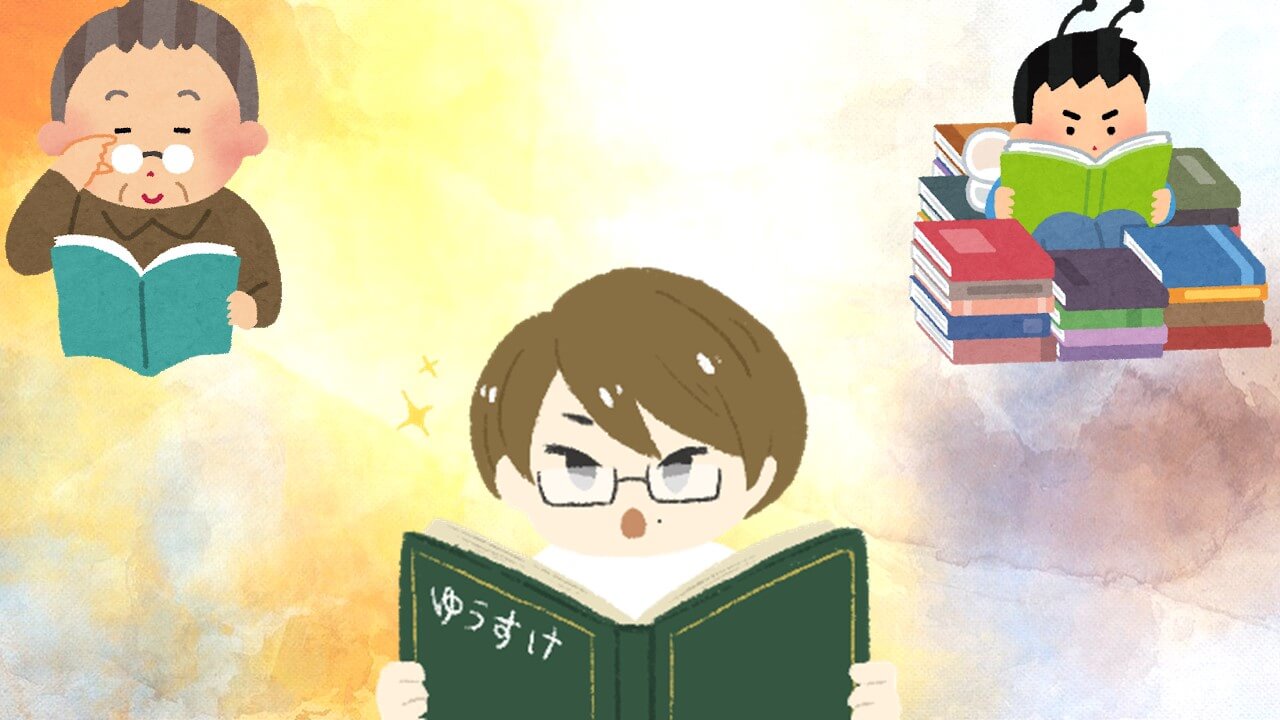
「読書は勉強になる、だから本を読む」だけだと大雑把なので、もうちょっと詳しく書いていきます。
勘違いされてしまうかもしれませんが僕は、文章を読む・文字を追うこと自体は、むしろ嫌いで、あまりやりたくない作業です。
さっきまでの話とは矛盾しているように聞こえますが、僕が楽しいと感じるのは「頑張って読んだらいいことがある」そんな感覚です。
 ゆうすけ
ゆうすけ
僕が大好きな水野敬也さんの『夢をかなえるゾウ』には「楽なもので体にいいものはほとんどない」と書かれています。
楽じゃないけど、楽しい。
だから読むんです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
世の中って割とすべて競争でできていますよね。
- 受験
- 就活
- 出世…etc
「どうやったら周りと違う結果が出せるか?」って考えたら当然、周りと違う「楽じゃない」ことをやるしかないと思うんです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
理由2:情報量が多い
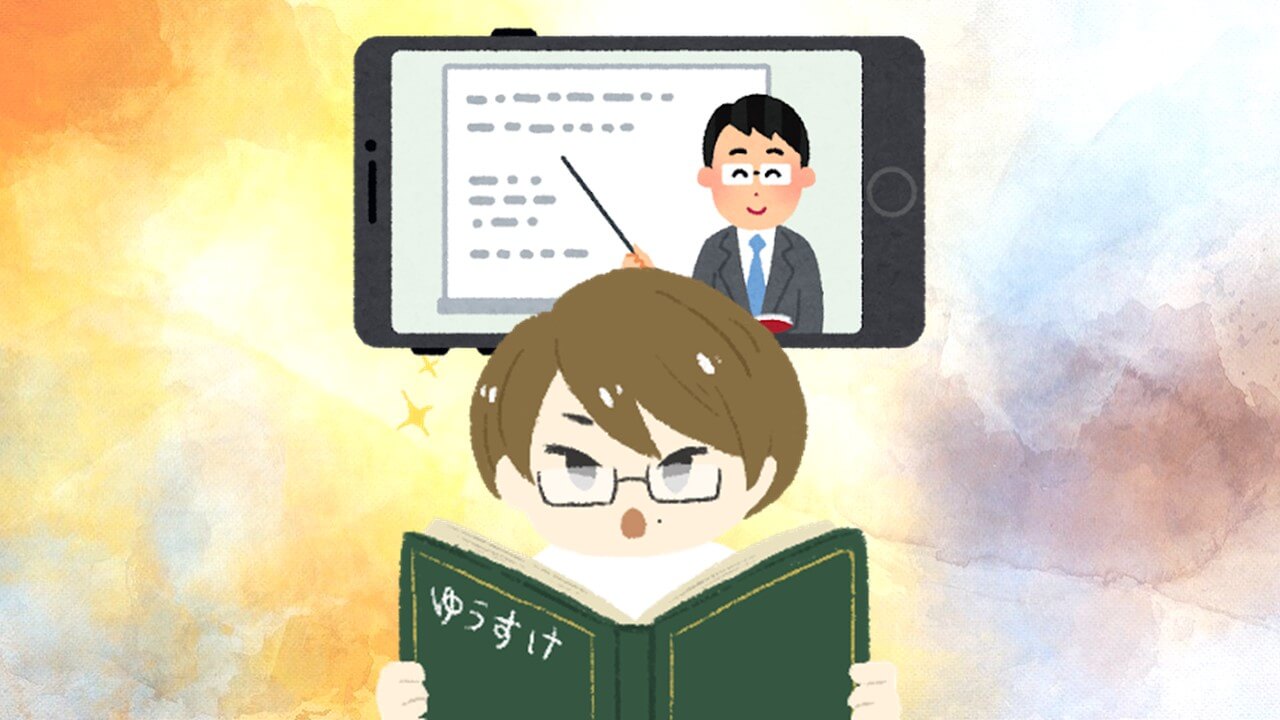
とはいえ、いまは勉強になる系の動画もたくさんあります。
ただ「基本的に」、動画よりも本が優れている点のうちの一つは「情報量の多さ」です。
もちろん動画の内容や再生速度にもよりけりですが、普通2時間の動画を見るより、2時間読書をした方が多くの情報が得られると考えていいと思います。
たまに「動画は情報量が多い」なんて言われますが、それはデジタル情報(この動画は●ギガバイトとか..)でのデータ量の多さであって、「情報量」においてだけ言えば、本の方が多いことがほとんどです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
1冊の本をオーディオブックで聞こうと思ったら何時間もかかるわけで、話し手の表情とか、抑揚などの情報を削ったら、本の方が情報吸収率は高いでしょう。
理由3:文字でしか残っていない

あとは、そもそも作者が直接手掛けたものが本しかないという理由もあります。
動画が流行りだしたのなんてここ最近の話で、これまで人間は文字で自分の考えとか歴史を残してきましたわけです。
先人たちの知恵を借りようと思ったら、本しかない場合があるということです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
物書きの人って一文一文に気を配って書いていると思うんですね。
特に書き出しの一文は一番神経を使うところで
吾輩は猫である。
夏目漱石『吾輩は猫である』
恥の多い生涯を送ってきました。
太宰治『人間失格』
などなど、小説の書き出しワンフレーズが有名だったりするわけです。
太宰治の『人間失格』について知ろうと思ったら、映画化されたものを見るのもいいけど、作者の言葉をストレートに知りたいと思ったら、本を読むしかないということです。
まとめ
ここまでいろいろと書いてきました。今の時代において、動画とか、セミナーとか、オンラインサロンではなく、本で勉強することのメリットは
- 楽じゃないから
- 情報量が多いから
- 文字でしか残っていないから
この3つかなと思います。
何より読書してるってかっこいいことだなーっと思うんです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
電車に乗ってるときとか、年配の方が難しそうな本を読んでるのをみると「いいなー。おれもそんなおじいちゃんになりたいなー」って思うんですよね。
将来は、「あのおじちゃんに聞けば何でも答えてくれる」って子供から慕われるような、町の何でも屋おじいちゃんになれたら面白いなと思ってます。笑
僕が読書について発信する理由
「趣味は読書です」と言うと「真面目だな…」「正直興味ない..」と思われることが多いと思います(おれ調べ)。
それでも僕がブログやYouTubeで書評を発信するのは、つまらなさそうな顔をする人ではなく、
「どういう本を読むの?」と興味を持ってくれる人と一緒にいたいなと、僕は思うので、こうやって情報発信しています。
 ゆうすけ
ゆうすけ
実際「読書が好きな理由」は「好きだから」でしかないんです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
それは、「好きだから」でしかないわけです。
今は誰でも好きなことを好きなように発信できる面白い時代なので、これからも発信していこうと思います!
 ゆうすけ
ゆうすけ