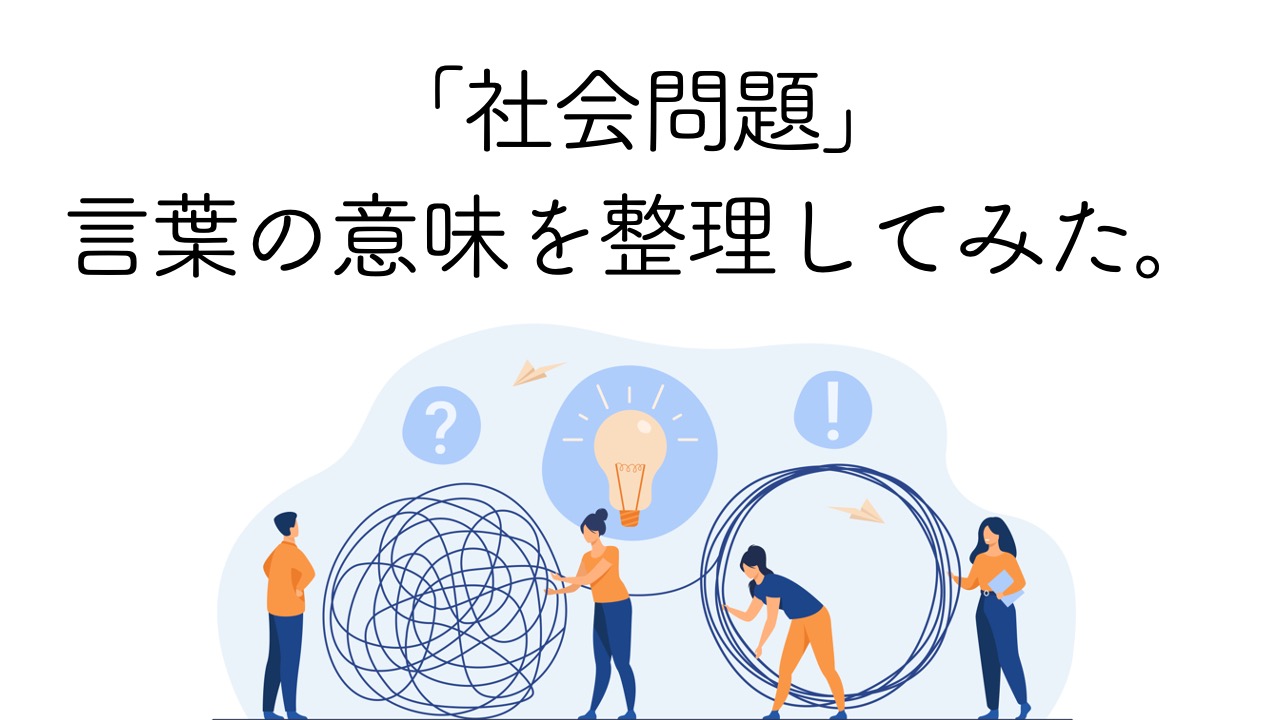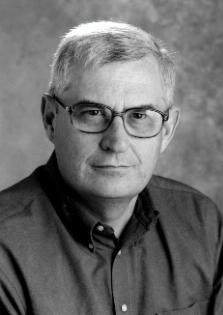ゆうすけ
ゆうすけ
参考文献:社会問題とは何か: なぜ、どのように生じ、なくなるのか? (筑摩選書)
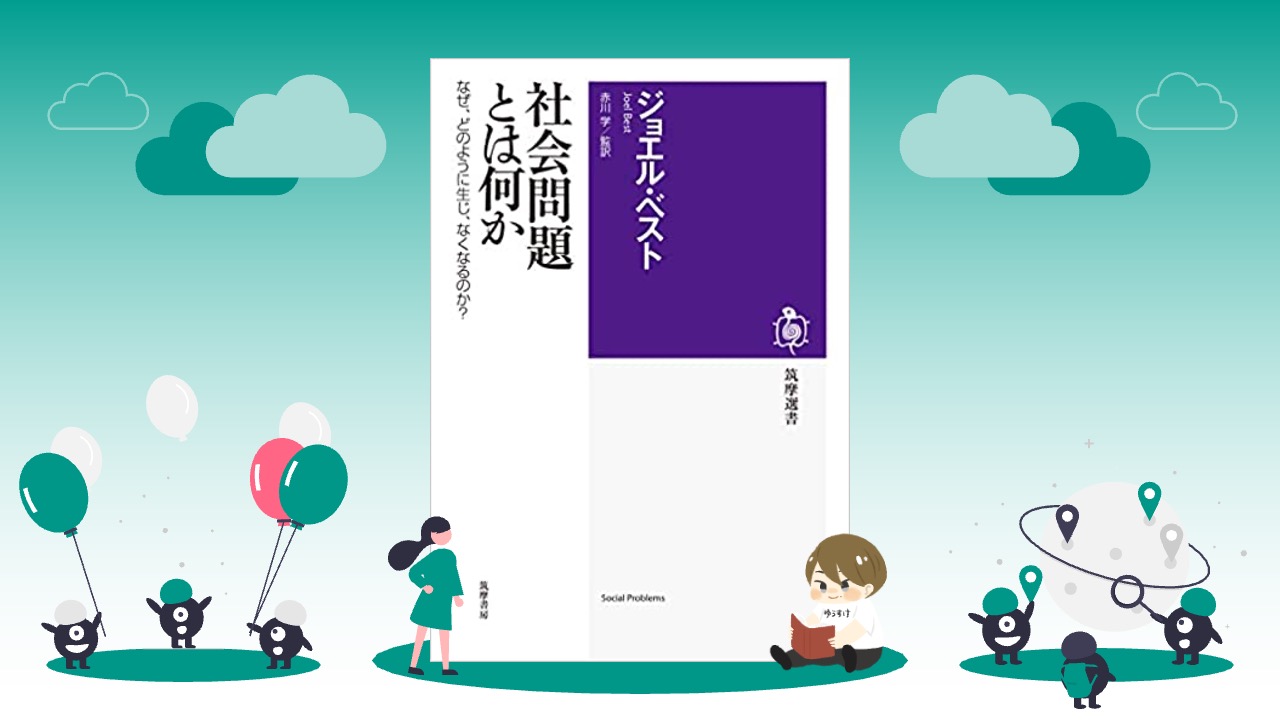
内容紹介
組織犯罪、あおり運転といった社会問題が人々に認識され、展開し、収束する過程を6段階に分けて考えることを提唱。社会問題を考えたい人にとり最適の入門書!
目次
社会問題の定義
社会問題とひとことに言っても、「犯罪、自殺」も社会問題だし「気候変動」も社会問題です。
非常にぼんやりとした「社会問題」と言う言葉ですが、これをどう定義するのか。そのアプローチの考え方には「客観主義」と「主観主義」があります。
客観主義

「社会問題とは?」に対するよくある答えは、社会問題を「何らかのかたちで社会に害を与える状態」と定義することです。
本書ではこのように定義するアプローチを「客観主義」と呼んでいます(客観的に測定できる状態から定義付けしているから)。
客観主義の考え方は、一見なにも問題がないよう(誰もが思い浮かべる定義)に思えますが、著者は客観主義には三つの注意点があると指摘しています。
- 有害と思われている状態が必ずしも社会問題と認識されない
- 同じ状態がまったく異なる社会問題として認識される
- 非常にさまざまな現象が含まれる(そもそも定義が広すぎて意味ない)
第1 必ずしも社会問題と認識されない

例えば、「性差別」の問題は、人間の長い歴史を考えるとごく最近になって社会問題として認識されるようになりましたよね(性で差別する構造は長い歴史があるにもかかわらず)。
「性差別は不公平である」と言うのであれば、身長についてはどうでしょう?いくつかの研究では、背の高い人がさまざまな点で有利であることが示されており、背の低い人が不公平な立場にあるけど「身長差別」という言葉はほとんど聞きません。
このように、問題はそこにあるのだけれど、社会問題として認識されていないものもあります。
第2 異なる問題として認識される

とあるニュース解説者が「現代社会は肥満の人を差別している」と主張するとします。体重が重い人は仕事を見つけるのが難しい、軽蔑の対象となる、などの主張です。
しかし他方では「肥満自体が不健康であって、肥満は社会に対してさらなる多額の医療費を負担させているという」主張もありえるでしょう。
この二つの主張は同じ「肥満」を社会問題と捉えているにもかかわらず「見た目の問題か」「医療費の問題か」でまったく異なる理由や論点で認識されることがわかります。
ニュースを見ていて「それ、論点ちがくね?」ってことありますよね。それです。
第3 定義広すぎ

社会問題を「何らかのかたちで社会に害を与える状態」というのは非常にさまざまな現象が含まれているような曖昧な定義です(つまり、ほとんど意味がない…)。
主観主義

「社会」が主語となっている客観主義に対して、「個人」が主語になって社会問題と捉える「主観主義」というアプローチもあります。
これは例えば、女性差別の構造を「正常で自然なもの」と考える人からすれば、女性差別は社会問題ではない。しかし「この構造は間違っている」と考える人からすれば女性差別は社会問題と考えるということです。
そしてこれは時代とともに変化する(実際、女性差別が取り上げられるようになったのはここ数十年の話で、それ以前は社会問題と考えていなかった)。
客観主義と比較するとこんな感じ。

「客観的な状態を見て社会に害を与えている」のか「主観的に見て社会に害を与えていると考える(考えない)」のかの違いです。
客観主義?主観主義?
著者は「社会状態に関する客観的な特徴に基づいて社会問題の有効な定義をみつよけようとするのは、無益な試みであるとわかる。」と書いています。
著者:ジョエル・ベスト
人びとが社会問題と考えることと社会問題と考えないことを区別しうる社会問題の客観的定義を考案することは、きわめて困難である。
それゆえ、あらためて問いたい。自殺と気候変動に共通するのは、いったい何なのだろうか。
(中略)
重要なのは、「ある状態が害悪を引き起こすのではなく、人びとがある状態を害悪だと考えている」ということである。
p21
「(客観的に測定できる)ある状態」に着目するのではなくて、「(主観的に)みんながその状態をどう考えているか」が大事ということです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
客観的には貧困は明らかに社会問題ですが、貧困が社会に役立つ側面もあり社会問題ではないという考え方もありました。
社会問題の過程

社会問題の過程
著者は社会問題の過程を六つの段階で想定しています(クレイム申し立てから始まり、政策の影響までが大まかな流れで、それぞれが相互している)。
- クレイム申し立て
社会問題が存在することをについてクレイムを申し立てる - メディア報道
より広く聴衆に届けるためにメディアはクレイム申し立て者について報じる - 大衆の反応
関心を寄せて支持するようになる - 政策形成
法律家や政策を形成する権力を持つ人びとが、問題に対応する新しい方法をつくり出す。 - 社会問題ワーク
政府機関は、さらなる変化を要求することをふくめて、新しい政策を実行する。 - 政策の影響
新しい構造に対して、さまざまな反応がみられる。

社会問題の型
最後に、著者が定義する「社会問題の型」がわかりやすかったので紹介します。
一人勝ち型
クレイムを申し立てからアレコレと議論されて徐々に認知されていくのが、社会問題の過程モデルでしたが、ほとんど抵抗を受けずにクレイムの受け手から瞬時に広く承認されるクレイムがあり、著者はこれを「一人勝ち型の社会問題」と呼んでいます。
例えば、児童虐待や児童ポルノ、子どもに対する脅威のクレイムはうまく受け入れられる傾向があります。こうした議論はとても説得的であるため、そのクレイムに反対する人びとを想定しにくい特徴があります。
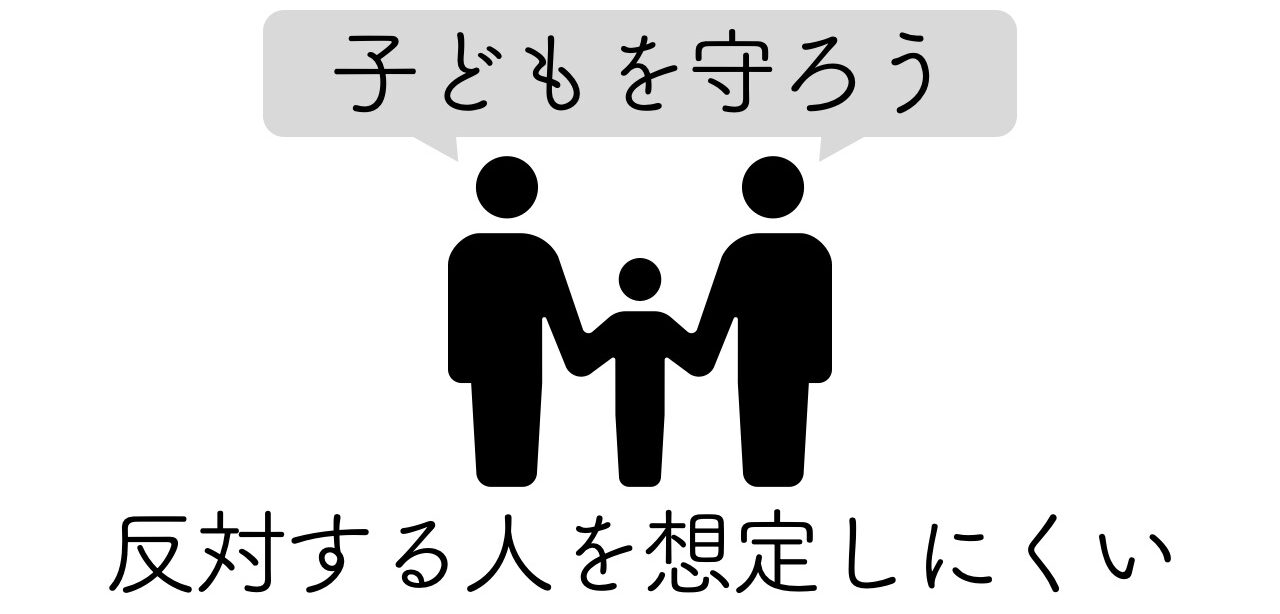
論争型
一方で、人によって意見が反対に分かれるような少なくとも反対者がいることを想定したクレイムもあり、著者はこれを「論争型の社会問題」と呼んでいます。
例えば妊娠中絶に関する論争は、「中絶は殺人であり、許されない」と主張する中絶反対派の人もいれば、「女性は自分の身体をコントロールすべきであり、それゆえ中絶は自由に選択するべきだ」と主張する中絶賛成派の人もいます。
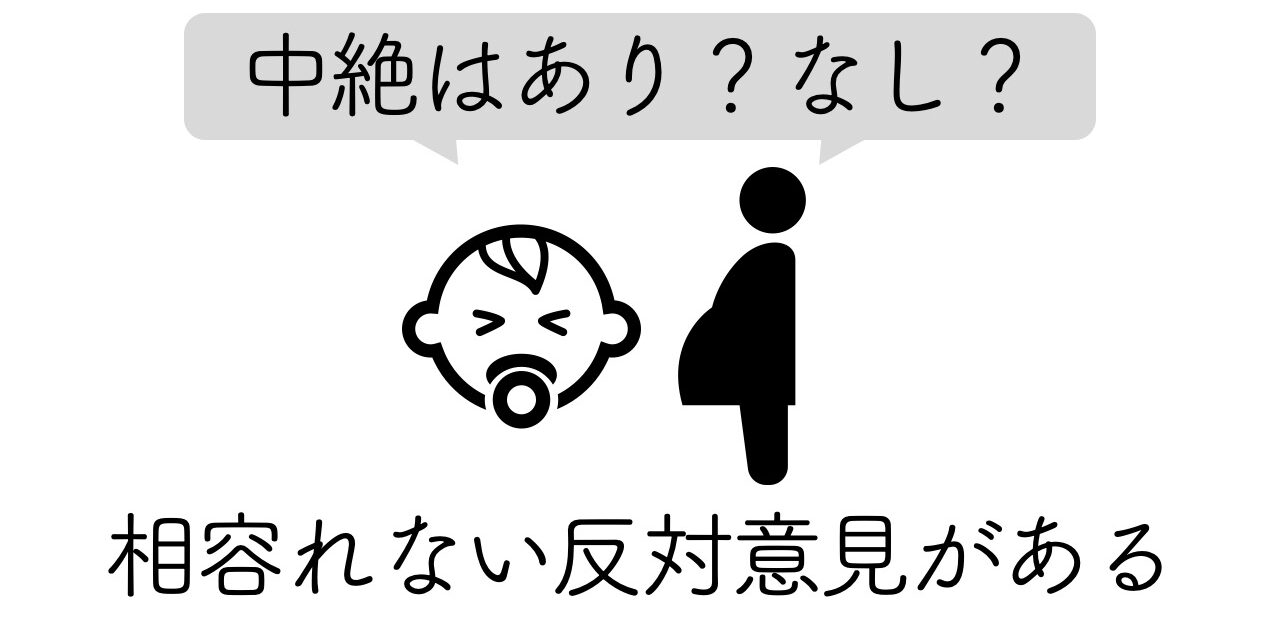
まとめ
定義:「客観主義」と「主観主義」
社会問題とは「社会に害を与えるもの」という誰もが思い浮かべる客観主義的な定義にはいくつかの問題点がある。そのため、僕ら個人個人がある状態をどのように感じるかという主観主義的なアプローチが必要不可欠です(客観的に害のある状態だとしても、それを必要悪だと考える人もいるため)。
過程:クレイム申し立てから政策の影響
クレイム申し立て→メディア報道→大衆の反応→政策形成→社会問題ワーク→政策の影響
型:「一人勝ち型」と「論争型」
社会問題には「反対する人を想定しにくい一人勝ち型」と「相容れない反対意見がある論争型」と分類できる。
 ゆうすけ
ゆうすけ