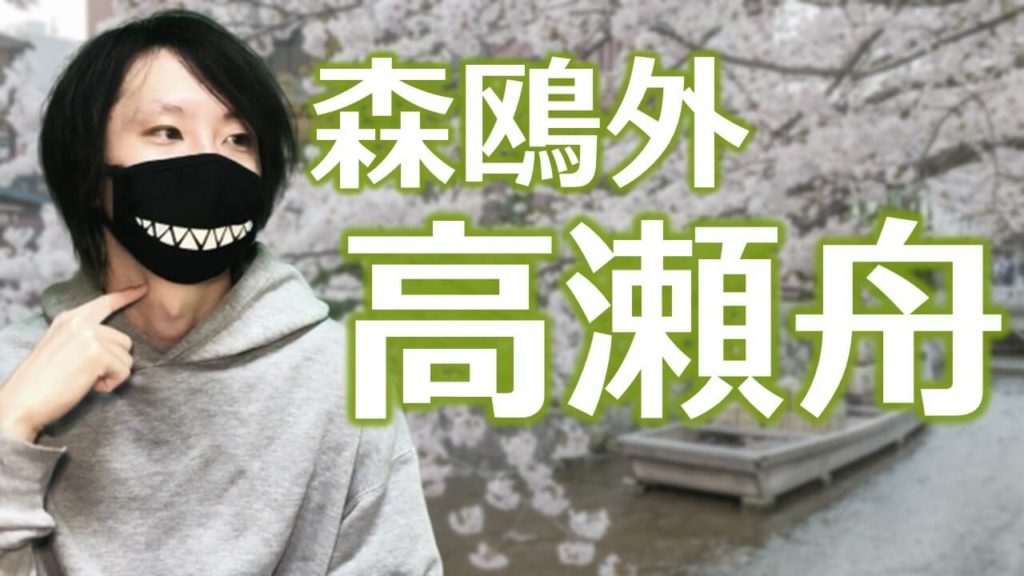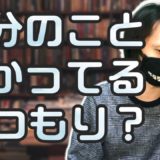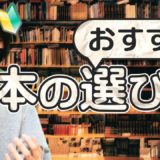\動画で見たい方/
 ゆうすけ
ゆうすけ
今回は、エレカシ宮本さんも好きな作家さん、森鴎外の『高瀬舟』を読んだのであらすじ・感想を書いていきます。
 ゆうすけ
ゆうすけ
- 森鴎外 著
- 1862-1922年の小説家
- 東大医学部を卒業・陸軍軍医となり4年間ドイツ留学を経る
- 軍医としての職務のかたわら『舞姫』『山椒大夫』などの名作を世に残した著者の基本情報
高瀬舟は青空文庫で読むことができます!
目次
『高瀬舟』あらすじ
高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。
書き出し
遠島の刑に処せられた罪人を、島に運ぶために高瀬舟が使われることがありました。
ある日、弟を殺した罪で喜助という男が高瀬舟に乗せられた。
喜助は罪人らしからぬ晴れやかで鼻歌を歌い出しそうな、そんな明るい表情をしていました。
不思議に思った護送の役人である羽田庄兵衛(はねだしょうべい)は理由を尋ねてみます。
おれはさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ
喜助はにっこり笑ってこう答えます。
なるほど島へ行くということは、ほかの人には悲しい事でございましょう。
しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。
喜助は、これまで過酷な環境にいて、そのような苦しみは、どこへ行ってもないだろうと言うのです。
仕事については身を粉にして働くけれども、もらったお金はいつも借金を返すか、食事のために物を買うかですぐになくなっていました。
 ゆうすけ
ゆうすけ
牢屋に入ってからは、仕事もせずに食べさせてもらうことができました。喜助にとっては劣悪な牢屋の食事でさえ、それだけで有難かったのです。
さらに牢屋を出るときに二百文(現代の2000~3000円)をもらいました。喜助にとってはこの二百文というお金が懐にあるというだけで幸せなことでした。
護送の役人は疑問に思いまた尋ねてみます。
お前がこんど島へやられるのは、人をあやめたからだという事だ。おれについでにそのわけを話して聞かせてくれぬか
喜助は、小さいときに両親を亡くし、弟と一緒に助け合って働いていました。
しかし、弟が病気で働けなくなってしまい、喜助は弟の分まで働くことになります。
ある日、いつものように家に帰ると、弟は布団の上で血だらけになっていました。
弟は、治りそうにない病気だから、早く死んで少しでも喜助を楽にさせたいという思いで、自ら喉に剃刀を突き刺したというのです。
「待っていてくれ、お医者を呼んで来るから」と喜助は言うのですが、
弟は怨めしそうな目つきで「医者がなんになる、ああ苦しい、早く抜いてくれ、頼む」と、喉に刺さった剃刀を抜いて死なせてくれと頼みます。
弟の覚悟に負けて喜助は剃刀を抜いて弟に死を与えました…。
森鴎外が問題提起したこと
ここまでが、高瀬舟のあらすじです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
紹介した文庫本では、高瀬舟に続き『高瀬舟縁起』が書かれています。これは森鴎外自身による解説(高瀬舟を書くにあたっての経緯等)です。
そこにはこの高瀬舟という物語は、翁草という随筆集から着想を得たと書かれています。そして、翁草を読んで森鴎外が大きな問題だと感じた点は二つ。
- 財産というものの観念について
- 死にかかっていて死なれずに苦しんでいる人を、死なせてやるという事
翁草を読んで感じた問題点と言うのがまさに、高瀬舟という小説に反映されています。
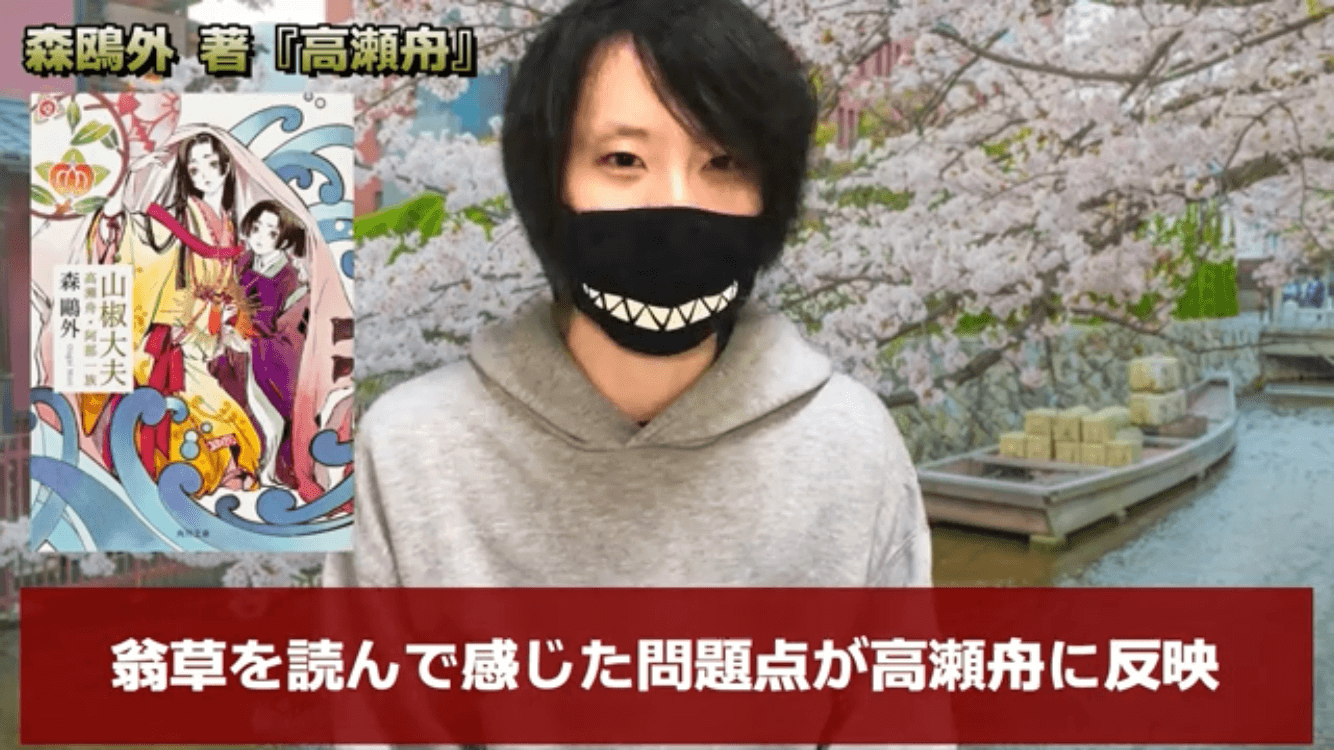
財産の観念について
人の欲には限りがないから、お金を持ったとしても、その限界というのは見出すことができない。
ただ、お金を持ったことのない人が、お金を持つ喜びは、その金額の大きさに関係しない。
二百文の財産でも喜助にとっては大きな喜びだったように。
 ゆうすけ
ゆうすけ
安楽死について
病気で苦しんでいる人がいたとして、その人を死なせてやるのは善なのか悪なのか?
従来の道徳では苦しませておけ(生かしておけ)と命じていたそうです。
しかし、医学社会ではそれとは反対に、楽に死なせてその苦しみから救ってやるがいいという考えがあり、これを「ユウタナジイ」というと書かれています。
このユウタナジイというのは、安楽死のこと。
海外では、安楽死の考え方は古くからあったのですが、森鴎外が生きた時代にはまだ安楽死という言葉がなく、この高瀬舟から概念が紹介されたと言われています。
人を殺すというのはどんな場合においてもしてはいけないことのはずです。
じゃあ、喜助のした行動って間違いだったのでしょうか?悪なのでしょうか??喜助は犯罪者でしょうか???
護送の役人は、喜助の話を聞いてこんなことを考えました。
そのままにしておいても、どうせ死ななくてはならなぬ弟であったらしい。
それが早く死にたいと言ったのは、苦しさに耐えなかったからである。
喜助はその苦をみているに忍びなかった。
苦から救ってやろうと思って命を絶った。
それが罪であろうか。
殺したのは罪に相違ない。
しかしそれが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じて、どうしても解せぬのである。
 ゆうすけ
ゆうすけ
命を粗末に扱ってしまうことと、個人の自由を尊重することの境界が難しい問題だと思います。
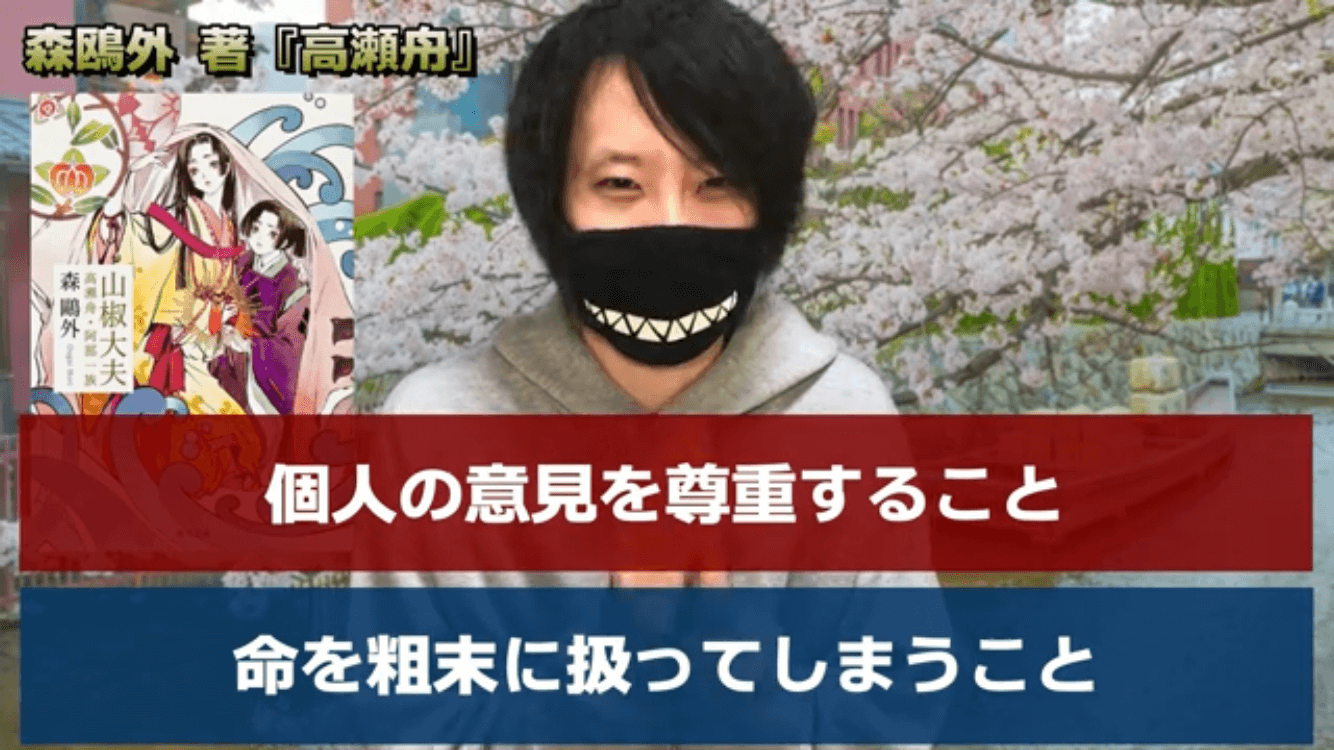
国や時代による安楽死に対する考え方
安楽死については国ごとに法律が異なっています。
キリスト教では「自殺は神への冒涜」だとされ、世界的にも当然、自殺はタブーなものとされています。
しかし、日本ではちょっと違うようです。
- 切腹:武士の名誉ある死
- 心中:究極の愛の形
- 戦死:愛国心を表すもの
このように「死」というものが崇高な死として神聖化されることがありました。
日本は諸外国に比べて自殺率が高いですよね。
これは、死に対して寛容だというようにも捉えることができます。
実際に、治る見込みのない病気にかかり苦痛に耐えられなくなった場合に、安楽死が選べるとしたら、選びたいと考える人が多いようです。
何が正解か?
護送の役人は、最後に何を思ったかというと…
自分では判断がつかないから、偉い人の判断をそのまま自分の判断にしようって思った、だけど腑に落ちないなぁってのが最後です。
 ゆうすけ
ゆうすけ
「死」は誰にでも訪れるものだけど、誰にも正解はわからないし、「コッチが間違いでアッチが正解」のように0-100の問題ではないということです。
今では「安楽死」という言葉は誰でも知っている言葉になっていますが、昔の人にとっては「自ら命を絶つ」ということは考えられない概念かもしれません。
「生きる」か「死ぬ」か、個人の意見を尊重して、自分で選べてもいいのでは?と議論が起こることが、豊かな証拠かもしれません..
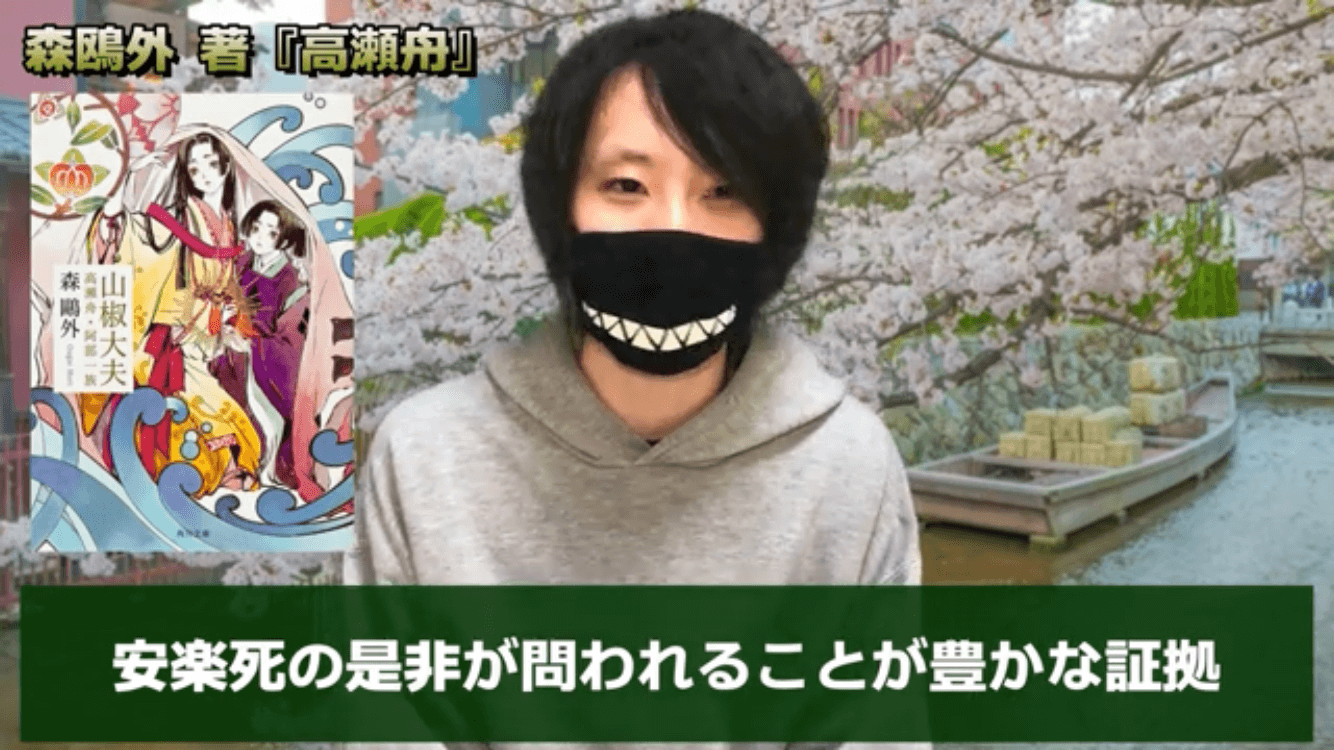
高瀬舟問題の僕の考え
『高瀬舟』を題材として学校のテストなんかで問われる問題は主に二つあります。
- 兄(喜助)がしたことは罪なのか?
- そもそも罪とはなんなのか?
やはり一番のテーマは、喜助が罪人なのか?ということだと思います。そして、それに伴い「罪ってなんだろう?」とうい疑問が想起されるわけです。
これは上記のように、簡単に「コレ!」と言った正解を見つけるのが難しい問題なので、ここでは大まかに二つの観点から考えてみます。
- 法律の観点:罪人
- 倫理の観点:罪人ではない
高瀬舟問題を難しくさせているのは、法律的には(やむを得ずとは言え人を殺すのは)アウトなんだけど、でも人間として(倫理的に)喜助のやったことって間違ってないよね?という法律と倫理の食い違いによるものです。
僕らは法治国家、つまり法律によってルールが定められているため、法律を破ることは決して許されません。だから、喜助は高瀬舟に罪人として乗っています。
しかし、法律は人間が作ったものである以上、完璧ではなく、時代によって塗り替えられていくものだという認識を持つことが大事です。
ある出来事によって、法律が改変されたり、新しく法律ができたりしますよね。
そして、人としての倫理や道徳(生まれながら人を殺してはいけないことを知ってる)というものは、人間の根源的なものであり、変わりにくく不変的なものだという認識も大事だと思っています。
- 人を殺してはいけない
- 人のものを盗んではいけない
- 人の嫌がることをしてはいけない
これら倫理や道徳を厳格に書かれているのが法律です。つまり「倫理に基づいて法律が作られる」ということ。
と、考えると、僕の結論はこうです。
現代のこの世の中のルール(法律)では、兄(喜助)は間違いなく罪人である。
ただ、それはあくまでも形式上の話であり、本来は罪人と決めつけてはいけないだろう。
そして、そもそも罪とは、人間が作った法律から外れた行為のことを指し、必ずしも倫理と一致しているわけではない。
まとめ
森鴎外の『高瀬舟』という短編について解説しました。
『高瀬舟』というタイトルからでは想像できない、ちょっと重たい、だけど大切なテーマを訴える小説でした。
短くてスグ読めるので、一度読んでみてはいかがでしょうか(高瀬舟を青空文庫で読む)
 ゆうすけ
ゆうすけ