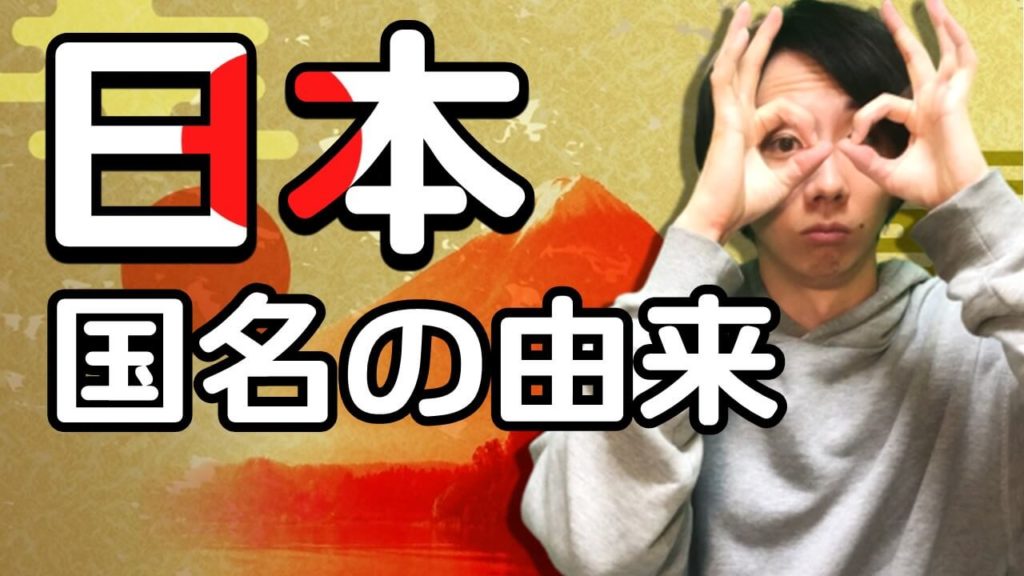ゆうすけ
ゆうすけ
百田尚樹さんの『日本国紀』をもとに、本書を参考に「日本という国名の由来」について話していきます。
目次
いつから日本?
「日本」と呼ばれるようになったのは、七~八世紀と言われています。いつが正式な始まりなのかは、はっきりとわかっていないそうです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
この二つの歴史書の編集を命じたのが天武(てんむ)天皇で、天武天皇が編集を命じたときには、日本という国号が正式なものとなっていました。
「日本」の意味
「日本」というのは、太陽が昇るところという意味である。
p54
日本の国旗は、白に真ん丸の赤で、日の丸と呼ばれますよね。
以前、聖徳太子についてまとめた記事で、聖徳太子が隋の皇帝である煬帝に宛てた手紙を紹介しました。
 【3分で解説】聖徳太子って何をした人?わかりやすく解説【仏教・憲法・遣隋使】
【3分で解説】聖徳太子って何をした人?わかりやすく解説【仏教・憲法・遣隋使】 日出る処の天子、書を、日没する処の天子に致す。恙無きや。
これは、「こっちの王(日本)から、そっちの王(隋)へ。お元気ですか?」という意味です。
このときから、日本は東アジアで最も早く日が昇る国である、ということに誇りを持っていたんですね。
また、日本が国名に太陽を入れたもう一つの理由は、日本神話に登場する最高神ともされる天照大神が太陽神であったからではないか、という考察もこの本には書かれています。
その前はなんと呼ばれていた?
日本はさらに昔、「倭」と呼ばれていました。
日本にはまだ文字がない時代のことは、中国の歴史書から推測されます。
三国志でお馴染みの「魏、呉、蜀」のうちの魏の国に関る書物『魏志』の中には、
- 日本がどんなところで
- どんな人がいるのか?
ということが書かれています。魏志倭人伝と言ったりしますよね(正確には『魏志』の中の「東夷伝・倭人の条」)。
 ゆうすけ
ゆうすけ
「倭」という文字は「小さい」とか「従順な」という意味です。
だから、当時の中国人は日本のことを「小さくて、従順な国だ」と言ったわけですね。
中国は、周辺国お国名や人物名には、賤しい意味を文字を当てたそうです。
例えば・・・
卑弥呼が治めていたことで有名な邪馬台国。
- 卑弥呼の「卑」
- 邪馬台国の「邪」
どちらも、決していい意味ではありません。
日本人は漢字を習得すると「倭」という文字がいい意味ではないことがわかり、同じ音を持つ「和」という文字を使うようになりました。
聖徳太子が定めた十七条憲法の第一条の書き出し
和を以って貴しと為し、忤ふこと無きを宗とせよ
にも「和」という文字が使われています。
日本はずっと「日本」
また、そこから名前を変えて日本と呼ぶようになりました。
先人たちは、「太陽が昇る国」という美しい名前を、そこからずーーっと使い続けてきました。
これ、僕ら日本人からすると当たり前の感覚ですが、何も当たり前のことではありません。
中国は「殷→周→春秋戦国→秦・・・」と王朝が変わってきたし、近代で言うと最近までロシアの国名は「ソビエト連邦」でしたよね。
そうやって、世界中各国で、国名が変化していく中で日本はずっと日本。
いや、ぶっちゃけ、僕の学の無さがバレるのであまり言いたくないですが、「国名が変わらないことって凄いことなの?」という感覚もありますが、
でも「太陽が昇る国」ってなんかカッコイイし、その名前を先人たちは、大切にしてきたんだと思うと、自分の国名とか、自分が日本人だということを誇りに思う気持ちも少し芽生えます。
本書紹介
この本、まだ1~2割くらいしか読めていないのと、僕が世界史・日本史に疎いこともあってか、この本を読んでいると、日本独特の文化に気付くことができて、「日本っていい国やん」と思える本だと思いました!
歴史に関わらず物事を見るときは「切り取り方」や、「違う角度からの見方」が大切で、一冊の本だけで知った気になるのは危険だと思いますが、「日本っていいな」と気持ちよく読める本です。