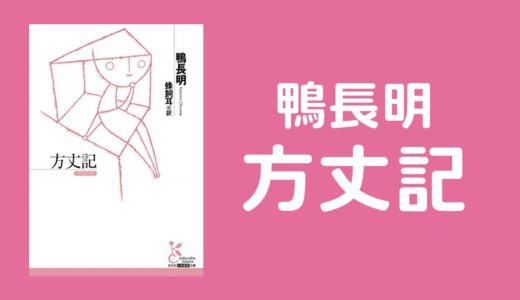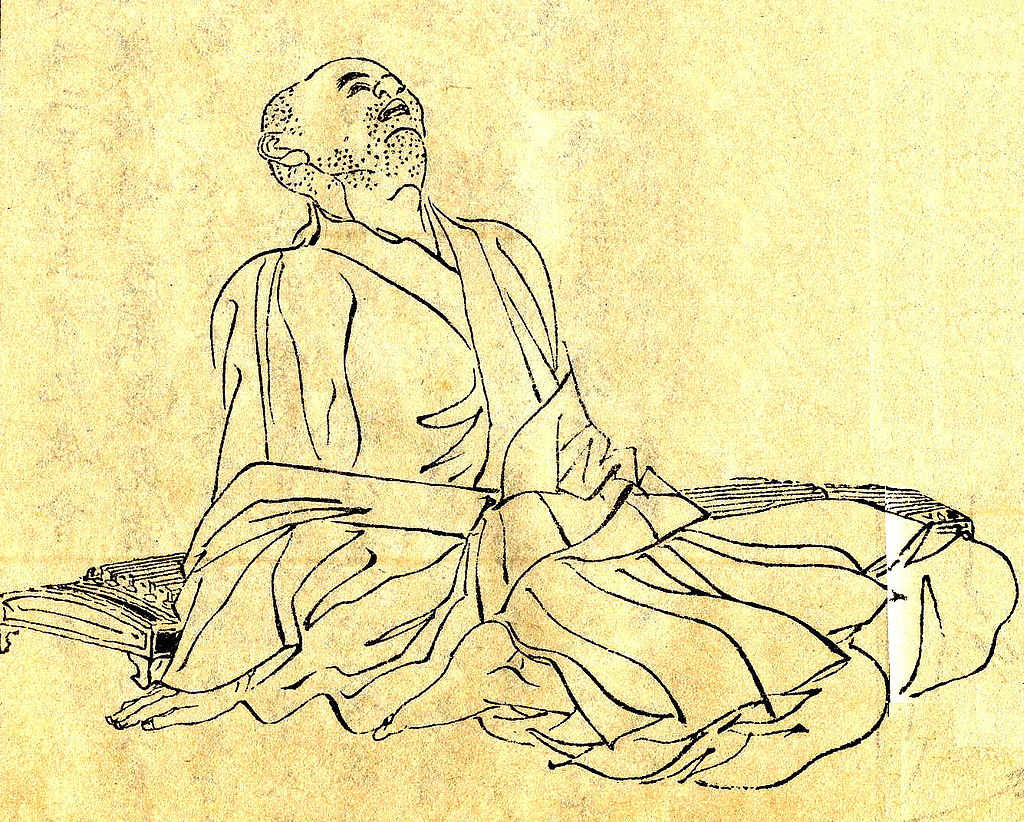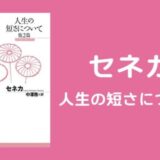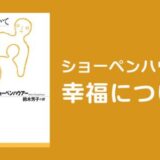鴨/長明
1155‐1216。随筆家・歌人。歌人として活躍し、後鳥羽院による和歌所設置に伴い、寄人に選ばれる。
琵琶の名手でもあった。1204年(50歳)、和歌所から出奔し(河合社禰宜事件)、出家遁世する(法名は「蓮胤」)。『新古今和歌集』に10首入集
目次
鴨長明『方丈記』の要点解説
方丈記の冒頭
方丈記は、鎌倉時代の歌人である鴨長明によって書かれた随筆で、清少納言の「枕草子」、吉田兼好の「徒然草」とともに、三大随筆に数えられます。
方丈記を読んだことがない人でも、冒頭をなんとなく聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。」
絶えず流れる川の流れと、その水に浮かぶ泡が消えてはまた浮かぶ様子に例えたものです。

すべてのものは、儚く移り変わっていき、とどまりはしないという、仏教的無常観が反映されています。
「無常」というのも文字通り、常では無い。つまり、一定のままではなく、世の中は変化し続けているという仏教の考えです。
当時の無常観
日本の地理的な特徴として、自然災害が多いことがあります。地震、津波、台風、火山の噴火・・・。
もちろん、鴨長明が生きた時代にもこれらの天災があり、容易に想像できるように、現代よりも、その被害は大きいわけです。
現代の火事というと、一軒のおうちだけが燃えるような、ニュースでそんな映像を見ますが、当時は、消火するのも時間がかかるし、家が木造でできているため、燃え移って大火事になることが普通でした。

現代のように食べ物の保存が簡単にできるわけもなく、お米は一年かけて作るため、途中で地震や台風、火山の噴火で、田んぼが崩れたら、お米が育たず飢えてしまいます。
立派なおうちを建てたところで、台風ですっ飛ばされたり、火事で焼けこげたり、一生懸命お米を育てていたら、台無しになったり、、、世の中は無常だという考えに落ち着くのも納得がいきます。
自分はちっぽけな存在であり、かわるがわる変化していく環境の奴隷なんだと、鴨長明は達観して世界を捉えていたように思います。
光文社古典新訳文庫の訳
方丈記は、全体を大きく分けると、前半には、鴨長明自身が20代から30代にかけて経験した災いの数々について書かれており、後半では、鴨長明が生まれ育った環境などが書かれています。
鴨長明の幸福感
権勢のある者は欲深くて、心が満たされるということがない。誰とも関わらない孤独な者は、後ろ盾がないことから軽んじられる。
財産があれば心配が多くなるし、貧乏なら悔しさや恨みの気持ちが去らない。人を頼りにすれば、その人の言いなりになってしまう。
人を養い育てると、自分の心が愛情に振り回されてしまう。世間の常識に従えば、苦しくなる。従わなければ、まともではないと思われてしまう。
どんな場に身をおいて、どんなことをして生きれば、しばらくの間だけでも、この身と心を安らかにさせておくことができるのだろうか。
p34
お金を手にしても、次は失うことが怖くなったり、常識に沿った行動をすれば「つまんない」と感じるくせに、常識から外れると恥ずかしくなったり、恋人がほしいと思っていて、できたとしても、その人間関係で頭を悩ませたり・・・。
「もっとこうなれば・・・」の「もっと」を手に入れたところで、完璧に満足できないのが人間です。
どれだけ権力があっても、お金を持っていても、心が安らかでなければ、それは別に幸せじゃないよね、と。こんなことが書かれていました。
やどかりは、小さな貝を好む。その方がよいと知っているからだ。私もまたそれと同じだ。
世間に近くに住むことがどういうことか、どうなるか、すでに知っているから、もう何かを望むこともないし、あくせくすることもない。
ただ、静かに暮らすことだけを考え、余計な心配のないことそのものを楽しんでいる。
p45
感想
世界というのは無常で、今日立派な家を建てても明日吹っ飛ぶこともあるし、権力やお金を持っていたところで、心の持ちようで、それが心配事となる。
鴨長明はそれを知ってるから、「静かに暮らすことを楽しもうぜ。」みたいな。現代で言うミニマリスト的な生き方・考え方だなと思いました。
人間の素直な欲望に従ったら、いい家は欲しいし、権力もお金も欲しくなると思うんですよね。
別にそれが悪いってわけじゃないけど、それは人参をぶら下げられた馬の状態ではないだろうか?
自分が人参をぶら下げられた馬だと、達観してみることができたら、また考え方は変わってきますよね。
方丈記は、どの時代でも当てはまるような、人生の生き方について、「こんな世の中だけど、あなたはどう生きるの?」と問いかけているような気がします。