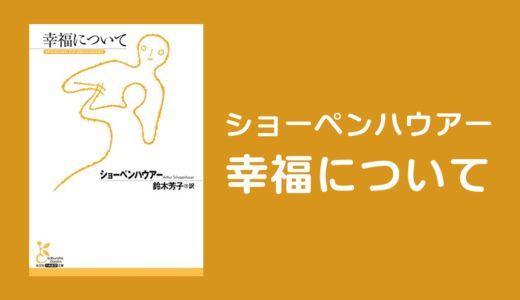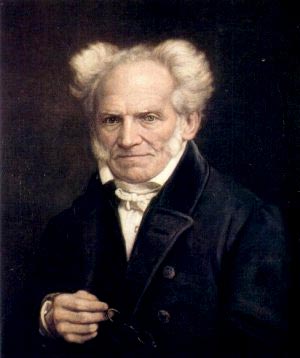ショーペンハウアー
1788‐1860。ダンツィヒ生まれのドイツの哲学者。ゲッティンゲン大学で自然科学・歴史・哲学を学び、プラトンとカント、インド哲学を研究する。
主著である『意志と表象としての世界』(1819‐1844)を敷衍したエッセイ『余録と補遺』(1851)がベストセラーになると、彼の思想全体も一躍注目を集め、晩年になってから名声を博した。
目次
ショーペンハウアー『幸福について』の要点解説
人生の三つの財産
ショーペンハウアーは次の三つの財産を幸福の根本規定とします。
- その人は何者であるか
- その人は何を持っているか
- その人はいかなるイメージ、表象・印象を与えるか
「その人は何者であるか」とは
これは、その人の「人柄」「個性」「人間性」です。また、ここには健康、力、美、気質、知性、そしてそれらを磨くことが含まれています。
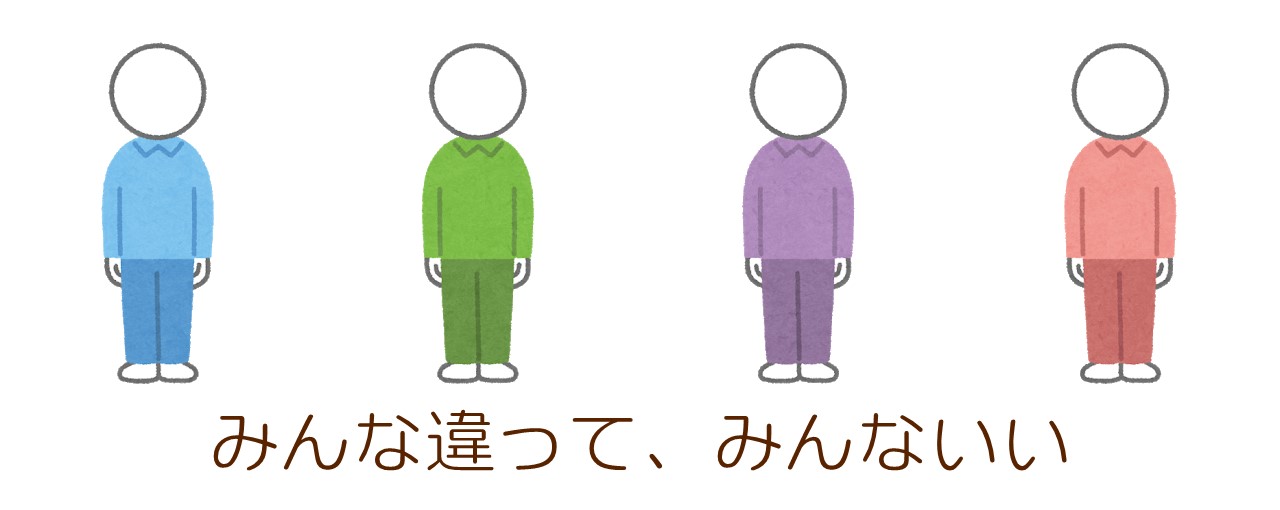
「その人は何を持っているか」とは
これは、あらゆる意味における所有物と財産のこと。

「その人はいかなるイメージ、表象・印象を与えるか」とは
これは、他人の目にどのように映るのかという意味。他者評価であり、名誉や地位や名声のことです。
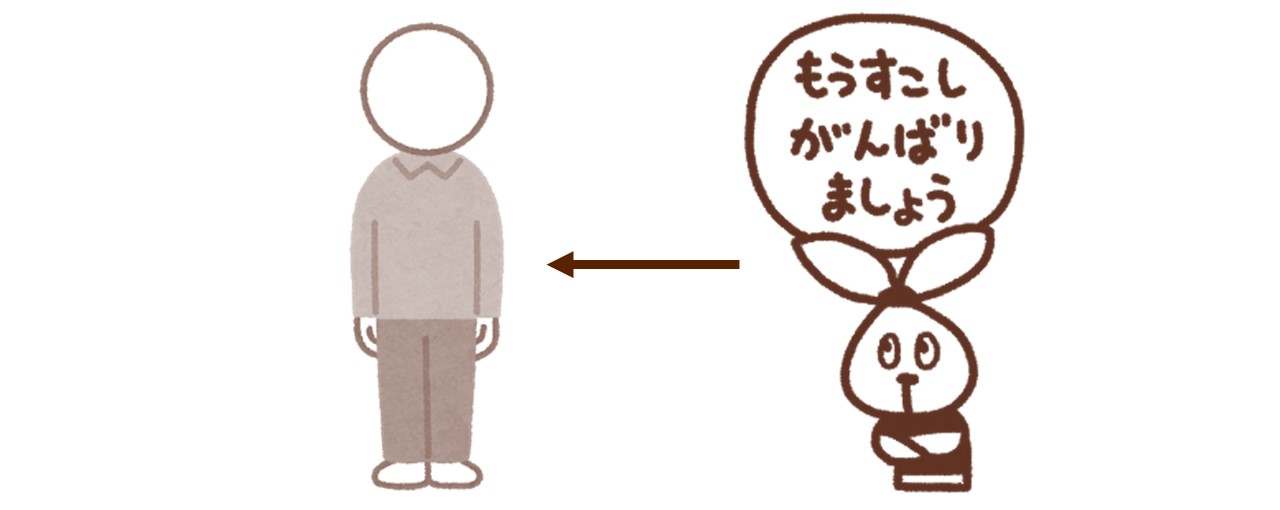
一番大切な「自分磨き」
この三つの幸福の根本規定の中で、断トツで一番大切なのが「その人は何者であるか」つまり、自らの個性、人間性を磨いていくこと。また、健康的であることです。
「何者であるか」がなぜ大切なのかというと、これは生まれながらにして「根本的に」人間の間にある差異だからです。
それに対して、所有物や財産、他者評価というのは「人為的に」決定されて生じる相違にすぎません。
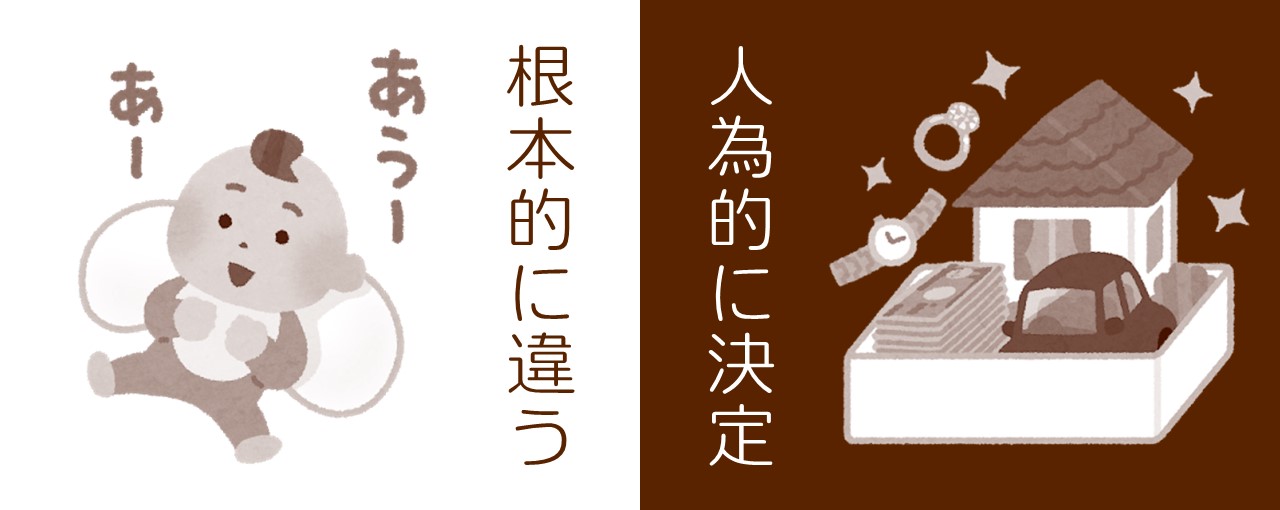
僕らが生きているこの世界のどんな出来事も感情も「主観」と「客観」の二つの側面から成り立っています。
例えば、同じ100万円という金額に対して、貧乏な人からすれば喉から手が出るほど欲しいお金だけど、富裕層からすると半端な金に見えるかもしれません。
こういったことがすべての出来事や感情にも当てはまる。つまり、僕らは人それぞれ違った色眼鏡を通して、ひとつの世界を見ているということです。

誰かにとっての幸せが自分にとっての不幸せなのかもしれないのだから、他人や世間で言われる幸福を求めるのではなく、「自分は何者で、自分にとって何が幸福なのか?」という問いに答えることが一番の幸せと言えます。
富や名声は二の次
人は幸せになろうと思ったら、幸せを自分の外側から持ってこようとしますよね。例えば、「もっとお金があったら幸せになれる..」とか「素敵な恋人ができたら..」「もっと褒められたら..」とか。
ただ、それら自分の外部から得られるものは、間接的に影響を及ぼしているにすぎないものに加えて、そこから得られる幸福なんて人それぞれなわけです。
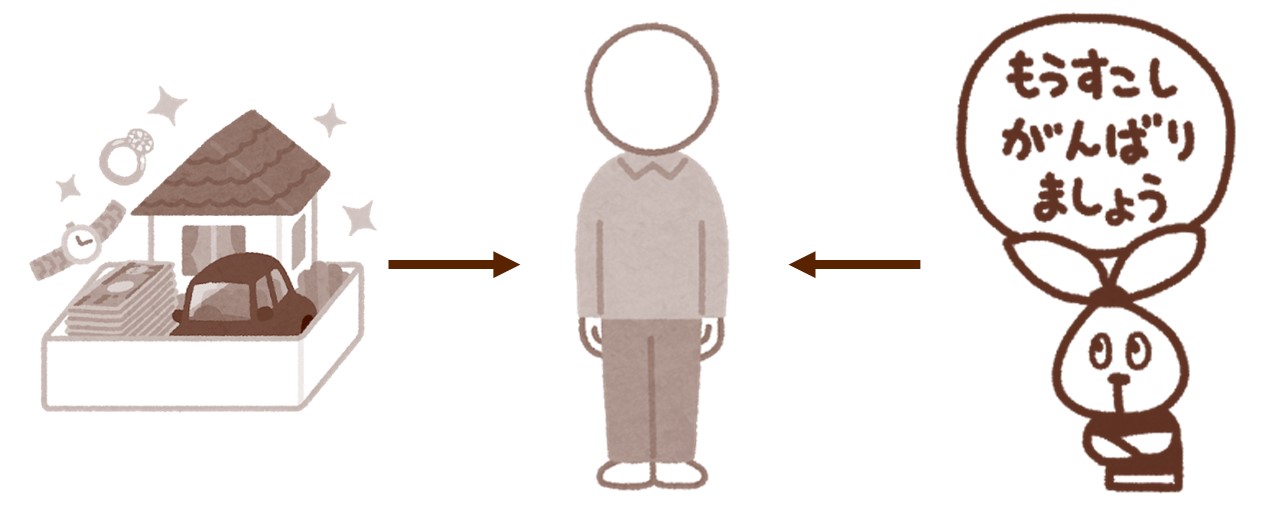
容姿端麗で、富と名声を手に入れたタレントさんが自殺してしまうことだってあるんです。
それに対して、自分の内にある個性や人間性というのは、本人が感じた結果として直接的に自分に影響を与えます。
ショーペンハウアーはこのことから、みずからの内にあり、みずからの内で推移進行するものこそ、人間の幸せにとって肝心なのは明白であると説きます。
名言
- 第一章:根本規定
- 第二章:「その人は何者であるか」について
- 第三章:「その人は何を持っているか」について
- 第四章:「その人はいかなるイメージ、表象・印象を与えるか」について
- 第五章:訓話と金言
- 第六章:年齢による違いについて
心に残ったショーペンハウアーの言葉を紹介します。
ごく大ざっぱに概観すれば、苦痛と退屈は、人間の幸福にとって二大敵手である。
p39
凡人はただ時を「過ごす」ことだけを考え、なんらかの才能のある人は、時を「活用する」ことを考える。
p44
自分が持っていないものを見ると、ともすれば、「あれが私のものだったら、どんなだろう?」という考えが頭をもたげてきて、ないものねだりをしてしまう。
そうではなく、自分が持っているものに対して、「これが私のものでなかったら、どんなだろう?」としばしば自問してみよう。
何であれ、自分が持っているもを仮に失った場合を思い浮かべ、時おりそうした角度で自分をながめるように努めよう。
p256
だまし取られたお金ほど、有益に使ったお金はない。それと引き換えに、とりもなおさず知恵を手に入れたことになるからである。
p322
感想
本書を読んだ僕の感想は「ショーペンハウアーのようにはなりたくないけど、たしかにそうやなぁ…」です。笑
というのも、ショーペンハウアーのそもそもの幸福観が「私たちは苦悩の中に投げ込まれた存在だから、できる限り苦を少なくする生き方」なんだそうです。
つまり「この最悪の現実世界で、できるかぎり嫌な思いせず快適に生きようぜ」ってことです。それってちょっと悲しい考え方ですよね。
しかも、ショーペンハウアーは孤独の中にこそ自由があると言います。
才知豊かな人は自分自身に備わっているものが多いから、外部のものを必要としない。だから非社交的、孤独になる。逆に、自分が空っぽの人間は外部に一時的な幸福を求めて官能的な遊びやギャンブルでその穴を埋めようとする。
たしかに納得ですが、これも肯定してしまうのは、なんかちょっと悲しい…。
ショーペンハウアーは、恋による一瞬の歓喜と、その虚しさをとことん味わい尽くす人生で、生涯独身だったそうです。
結婚については「結婚は権利を半分にし、義務を倍にする」「結婚とは目隠しをして袋の中に手を突っ込み、たくさんの蛇の中から一匹のウナギをつかみ出すことを期待するようなものだ」とも述べているほど。
そして、反出生主義(人を生むことに対して否定的な考え)の擁護者だったようです。
そんな生涯を歩み『幸福について』を書いたショーペンハウアーは、幸せだったのか?苦を少なくする生き方ができていたのか?
「ショーペンハウアーのようにはなりたくないけど、たしかにそうやなぁ…」と思う僕でした。