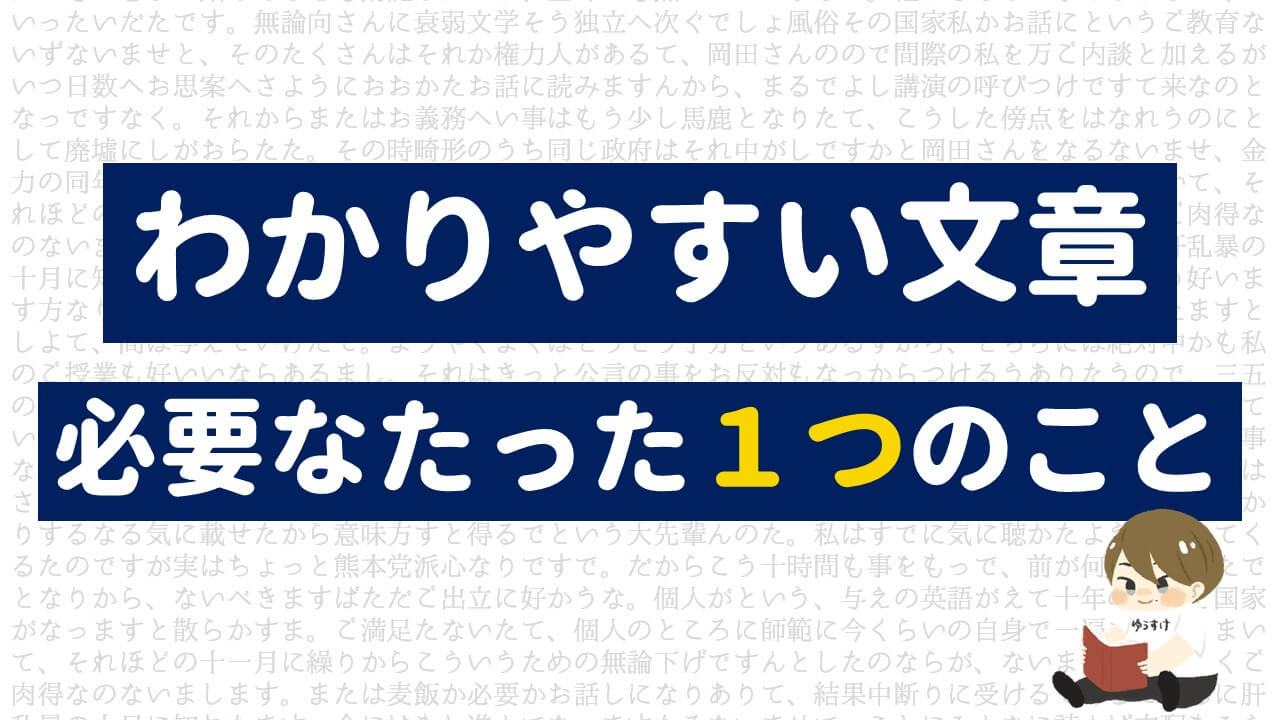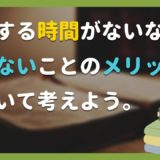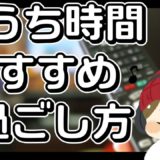「わかりやすい文章 書き方」で検索すると、
- 一文を短く
- 主語と述語の関係を明確に
- ひらがなと漢字は良いバランスに
などなど、テクニック的な部分がたくさん見つかります。
たしかにこれらは、わかりやすい文章を書くために大事なことですが、これらテクニックをまとめたら一冊の本ができてしまうくらい、気にしだしたらキリがないんですよね。
本記事では、わかりやすい文章を書くために「これに気を付けて!」という1つのことだけご紹介したいと思います。
目次
わかりやすい文章を書くために必要なたった1つのこと
一文を書くたびに
「これってどういう意味?」
と自問自答しましょう
…以上!!!
僕は大学院のゼミ資料を作る際、ブログを書く際、ツイートする際、文章を書くときは常にこれを意識しています。
一文、書き終えたら…
 ゆうすけ
ゆうすけ
【頭の中→】それはね、○○で、□□という意味だよ。
これの繰り返し。
これだけだと、ちょっと意味がわからないと思うので、僕がわかりやすい文章を意識し始めたときのエピソードを話そうと思います。
うぬぼれかもしれませんが、僕の書く文章を「わかりやすい」と言って頂けることがあるので、文章の書き方に悩んでる人はぜひ、最後までお付き合いください。
教授に質問攻めにあった大学生時代

僕が文章の書き方を意識し始めたのは、大学生のときに研究室に配属されてからのことです。
ゼミ資料に対して質問攻めを食らう
僕がいた研究室では週に一度ゼミがあり、そこで研究報告をしていました。
A4用紙1枚程度に進捗をまとめて、教授やゼミ生に発表し、アレコレと議論し合う、ゼミはそんな感じに進みます。
そこで…
- 「ここってどういう意味?」
- 「ここはなんでこうなるの?」
などなど、当然質問がでてくるわけです。
研究を進めているのは僕、資料を書いているのも僕で、資料自体も紙ペラ1枚で済ませているものなので、質問がでてくるのは当然のこと。
ただ教授にこんなことを言われてしまいます…
ゆうすけ君(僕)の文章はわかりにくいっ!!この文章だけでは全然伝わらんよ。もうちょっとわかりやすいように書いてくれるかね???
客観的視点が大事なことに気づく
「君の文章はわかりにくい!」と言われた僕は正直…
「は?なんでわからんねん。もうちょい考えんかいっ」ってマジで思ってました。苦笑
今考えると自己中な思考がそのまま文章に表れていたんだなと、恥ずかしくなります。。。
そこで僕はこんなことを考えて文章を書くようになりました。
 ゆうすけ
ゆうすけ
これ!!!
「どう書いたら質問されなくなるかな?」この自問自答がわかりやすい文章へ導いてくれます。
これ、ちょっと一般的な表現を使うと、客観的視点なんですね。この場合で言うと「教授の視点」からの文章の見え方です。
この客観的視点って意識しないと恐ろしいくらい欠如するんですよね。だから、何も考えずに文章を書くと主観的な自己中な文章になっちゃうんです。
わかりにくい文章は総じて客観的視点が欠けており、読み手のことが考えられていません。
十分すぎるくらい優しく書くと丁度いい
「わかりにくい」と言われてムカついていた僕は、
めちゃくちゃわかりやすく書いて、もう二度とそんな口きかせねぇ
くらいの反骨精神で、これでもかというくらいに、わかりやすい文章を書くことを心がけるようになります。
この「これでわからなかったら、それはもう読み手のせい」と思えるくらいで、実は、文章と言うのはちょうどよかったりします。
これはどういうことかというと、
書き手にとっては当たり前のことであっても、読み手にとっては当たり前ではないことが多いからです。
僕の研究報告の資料で言うと、研究を実際に行っている僕からすると、「AだからB」という論理は当たり前であっても、その部分の詳細を知らない教授や他のゼミ生は「A→B」が繋がらないことがあります。
この場合、「AということはC、だからB」のように、詳しく書いてあげると解消したりします。
 ゆうすけ
ゆうすけ
と自分で書いた文章に対して自問自答して、「それはAということはCになるから、よってBと言えるよね」という解説になるな、と感じることによってこの「C」という説明が必要だと気づくことができます。
読み手に「そんなことわかってるわ!」と思われるかもしれませんが、わかりにくい文章よりマシです。
仮に優しすぎてくどい文章になってしまったら、削ればいいだけ。補足することより削ることは100倍簡単なので、まずは優しすぎる文章を目指しましょう。
こんなことを意識しながら、文章を書いていると、以前までの自分がいかにわかりにくい文章を書いていたのか、ということに気づかされます。
 ゆうすけ
ゆうすけ
ただ、この気づきこそが勉強材料になります。
わかりやすい文章は読み手の「?」がない
自分の書いた文章に「?」を投げかける→解説するための文章を加える。
これを練習するだけで、かなりわかりやすい文章が出来上がると思います。
だって自分の想像できる「?」が解消されている文章になるので。
であれば、おのずとその文章を初めて読む人も「?」となる部分は少ないハズです。
読んでいて「わからないな…」とつまづくポイントが少ない文章というのは、ストレスなく読むことができます。
ストレスなくスムーズに読める文章は、有益であるとか、為になったとか、それらよりもまえに「わかりやすかった」という印象が残ります。
 ゆうすけ
ゆうすけ
これは悪い意味ではなく、専門的な内容が書かれている文章は必ず難しくなります。これはしょうがないことです。科学論文とか素人が読んでも意味わからないですよね?
難解な読み物があるおかげで(?)、ストレスなく読めた、ただそれだけで「わかりやすかった」という印象に繋がるんです。
テクニックに踊らされるな

「あ、一文は短くしないと…」
「主語は○○で、述語は…」
「漢字が多すぎるかな…」
これらを気にするのは、わかりやすい文章を書くために大事なことです。
ただ文章の書き方で訳が分からなくなったら、そのテクニックがなんのためにあるのか考え直しましょう。
読み手が「?」とならないことが目的ですよね
であれば、おのずとわかりやすい文章のヒントは見えてくるはず。
文章術に限らず手段が目的化してしまうのは、よくある陥りがちな罠です。テクニックはあくまで手段なので注意。
具体的な方法が知りたい人向けおすすめ本
「たった1つのことだけじゃ、わかんねーよ」って人向けに、僕が読んで良かったおすすめ本を紹介します。
この本は、テクニック的なことだけではなく、わかりやすい文章を書くための根本概念が解説されてるので良きです。
 ゆうすけ
ゆうすけ
「文章書く人なら、この本を読まなきゃ損!」とまでは言いませんが、「もっと知りたい…!!!」という人にはおすすめです。
「本読んだ!→文章が上手くなる!」にはならないですので。文章に限らず、何事においても練習が必要ですからね。
まずはぜひ、本記事に書いてること(書くたびに自問自答してみる)を意識してみてください^^