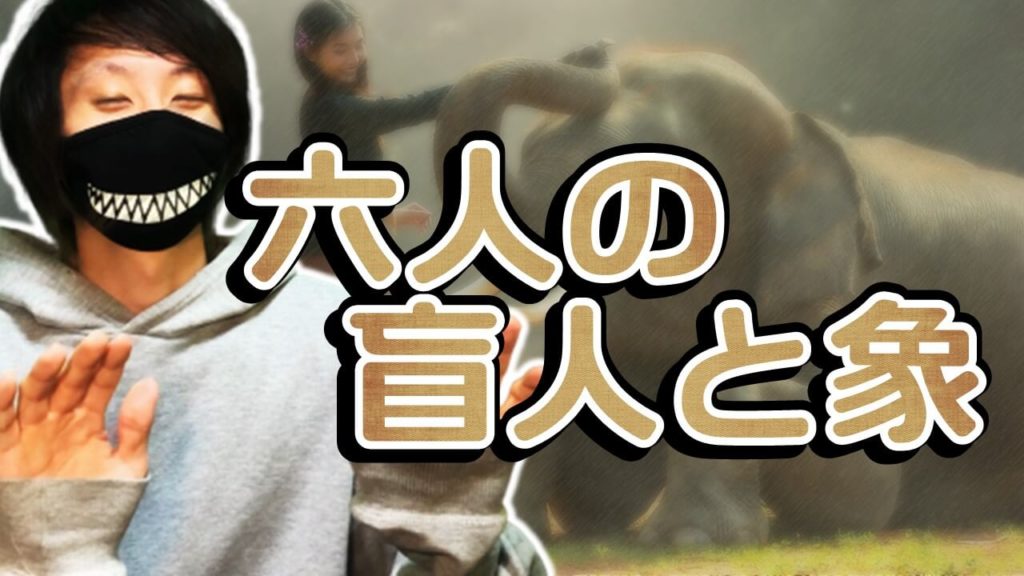\動画で見たい方/
 ゆうすけ
ゆうすけ
今回はインド発祥の寓話「六人の盲人と象」から得られる教訓についてお話します!
個人が誰でも発信できる今の時代において、大切な教訓が詰まっていました。

目次
『六人の盲人と象』あらすじ
ある日、目の見えない六人の盲人が象を触ってその正体を知ろうとしました。
1人目は、象の鼻を触り「象とはヘビのようなものだ」と言い、
2人目は、象の耳を触り「象とはウチワのようなものだ」と言い、
3人目は、象の足を触り「象とは木の幹のようなものだ」と言い、
4人目は、象の胴体を触り「象とは壁のようなものだ」と言い、
5人目は、象のしっぽを触り「象とはロープのようなものだ」と言い、
6人目は、象の牙を触り「象とは槍のようなものだ」と言った。
それから、6人の盲人たちは言い争い、それぞれが自分の意見を譲らなかった。

『六人の盲人と象』から得られる教訓
この物語では「物事の一部だけを知って、それがすべてだ思いこむな」という物事の捉え方の危険性を比喩しています。
 ゆうすけ
ゆうすけ
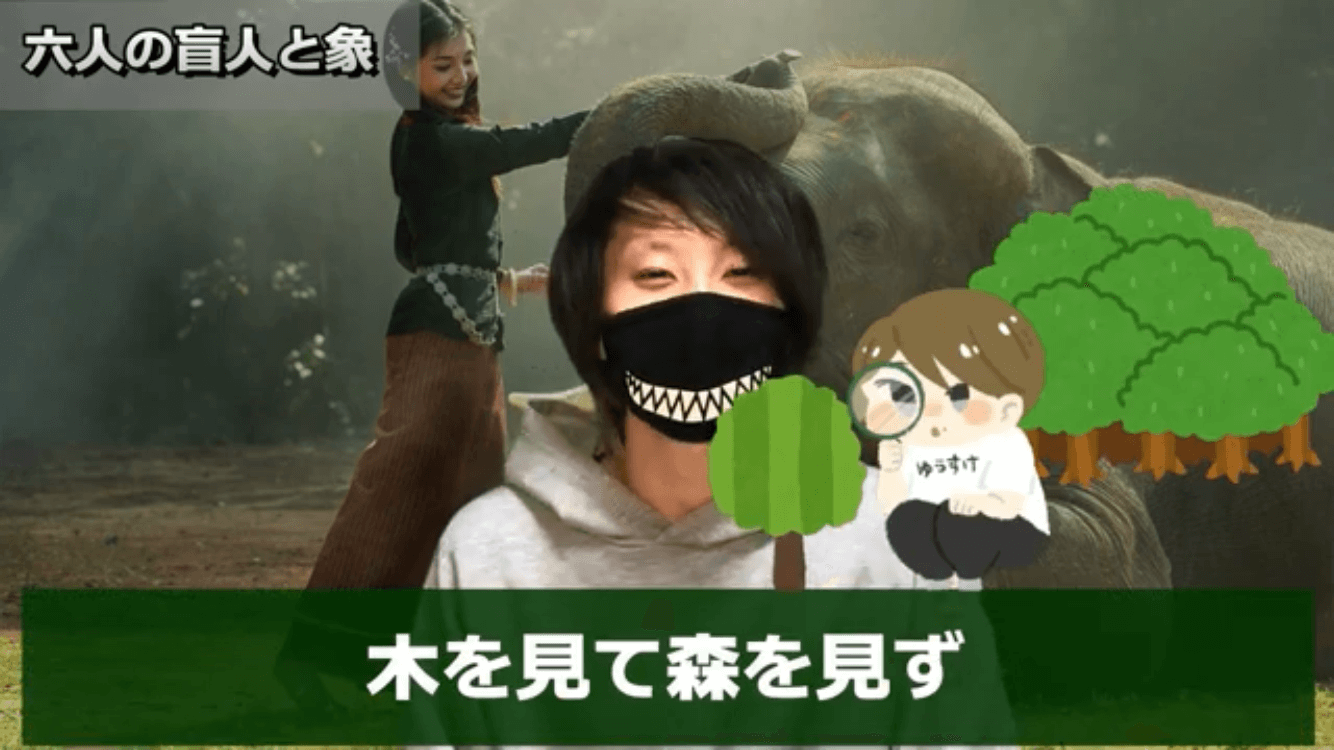
この物語の教訓として得られるのは
物事を多面的に捉えよう
ということで、それは例えば、
- 1冊の本を読んだだけで知ったような気になるな
- 本当か嘘かもわからないネット記事を鵜呑みにするな
- Twitterの1ツイートだけでその人の人間性を判断するな
などなど、僕らが何か見たときや知ったときなど、あらゆる場面で考えるべきことかなと思います。
盲人は愚かなのか..??
僕はこの物語を知ったときにたしかに
- 自分の無知さ
- 自分が知っていることなんてたかがしれている
これらの自覚を持つことは大切だと思ったんですけど、
 ゆうすけ
ゆうすけ
だって、多面的な視点というのはどこまでのことを言うのかはわからないし、世の中のすべてのことを理解するなんてできません。
 ゆうすけ
ゆうすけ
「何か意見を言えば、それはお前だけの小さな世界での話だろ!」ということになり、だからと言って何も意見しなければ「意見がない人間じゃん」という矛盾があるのかなと。

ただ、ここで大事なのは、六人の盲人はそれぞれ真実を言っているということです。
たしかに、象の鼻はヘビのようなものだし、耳はウチワのようなものであることには間違いないです。
僕なりの一番の教訓
だから、誰かに反対意見を言われたり、ネットで批判されたりしても
 ゆうすけ
ゆうすけ
と反抗するのではなく、
 ゆうすけ
ゆうすけ
くらいに受け流せればいいんじゃないかなと思います。
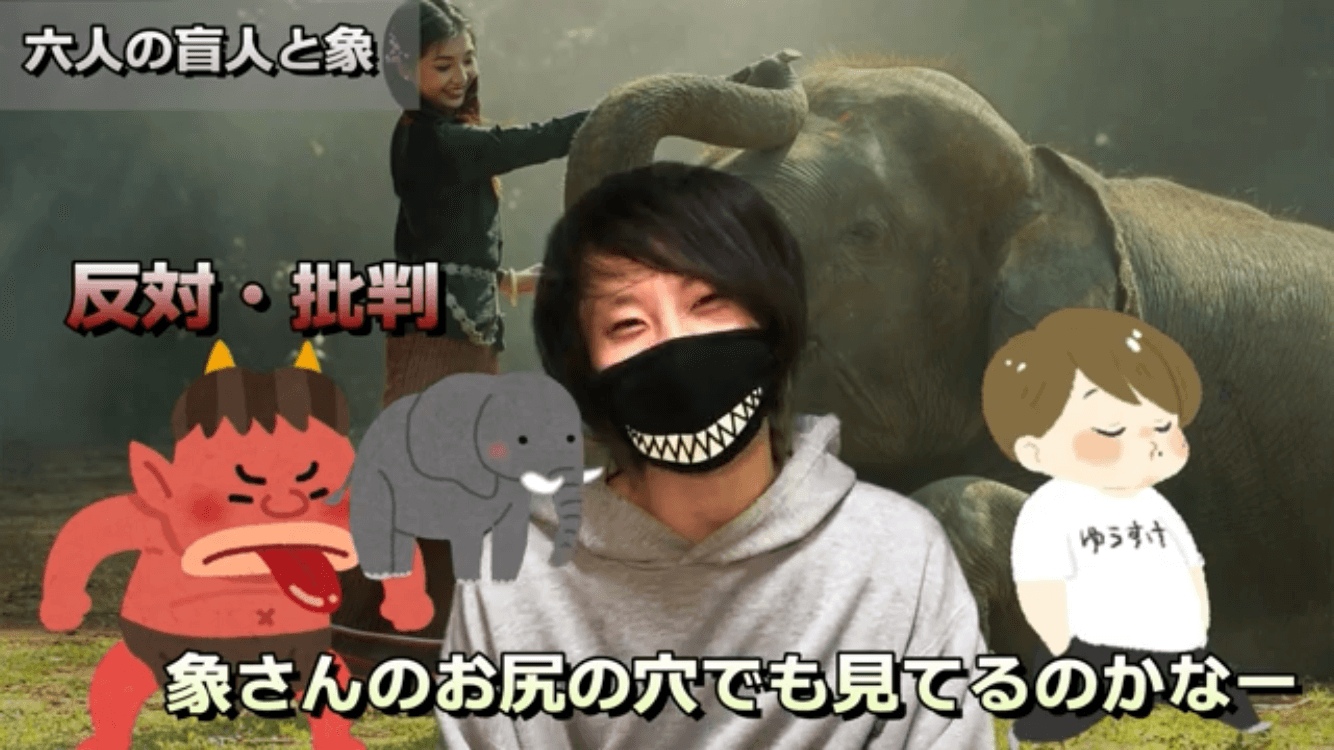
ひとりひとりの真理があって、他人の言葉は反対意見のように見えても、それは見ている角度が違うだけだと認識するということです
ちょっと話の趣旨は違うかもしれないですが、ドイツの哲学者カントは
人間はモノ自体には到達できない
ということを言ったそうです。
これは例えば、机の上にリンゴがあったときに、僕ら人間にとってリンゴは「赤」に見えているんだけど、別の生き物からしたらそれは「青」に見えているかもしれない。

だから、「リンゴは赤色」というのは唯一の真理ではなく、人間にとっての真理であって、リンゴそのものの本当の姿とはいえないということです。
青色に見えている生物に向かって「いやいや、リンゴは赤色だから」と議論したところで、その議論って全く意味がないよね、ということをカントさんは言ったそうです(解釈が違っていたらスミマセン)。
 ゆうすけ
ゆうすけ
まとめ
今回は『六人の盲人と象』という寓話から得られる教訓について話しました。
ちなみに、この寓話は「群盲象を評す」という言葉で表されたりします。
寓話って、ひとつの教訓をバシッと与えてくれるものだと思いますが、こうやって深堀りしていくと新たな発見があります。