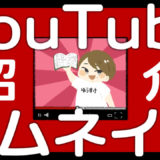お盆休みに実家に帰ったとき、家族みんなでバーベキューをした。
地面を見ると、アリが焼けた肉の破片をせっせと運んでいた。
目次
最初のアリが作る「正解」へのルート
アリがなぜ、綺麗な列をなして餌を運ぶことができるのか、についてはとても有名な話だ。
アリは餌を持つとフェロモンを出す(あ、僕は詳しいわけではないので、間違ったことも書いちゃってるかもしれないのでご注意を)。

このフェロモンは
- 揮発性(蒸発しやすい)
- 誘引性(文字通り)
の2つの特徴がある。これだけで、あの綺麗な行列ができあがる。
一匹のアリが餌を見つけて、巣まで持ち帰った通り道をフェロモンを使って記録することで、他のアリが続いて、最終的に行列ができるというわけだ。

ひねくれアリが導く、より優れた「正解」
大勢で行列を作って餌を運んでいるにも関わらず、外れた道で帰宅するアリがいるらしい。
こっちが正解だって、わかっていたとしても知らんぷり。そのアリが何を考えているか全くわからないけど。

そんな、ひねくれアリがたまたま、餌と巣までの最短ルートを通ったとする。
このとき、さっき説明したフェロモンの特徴である「揮発性」というのが上手く機能する。
すぐに蒸発する。ということは、餌と巣との距離が近いルートに残されたフェロモンの方が強く誘発ということになる。

すると今度は、新たに見つけた短い距離でのルートの方に、アリが行列を作っていく。
ひねくれアリのおかげで、より優れた正解が手に入るということだ。
世の中に溢れる「正解」
世の中には「正解っぽいもの」が溢れてる。
「こうすれば成功する!」
「こうすれば上手くいく!」
もちろん先駆者の言うことに聞く耳を持つことは大事だ。
ただそれは、ひとつの正解にすぎない。最初に見つけたルートと一緒。
ひねくれアリという「ゆらぎ」によって、規則正しく動くだけでは手に入らなった、より優れた正解が見つかることもある。
僕はこの「ゆらぎ」という現象が好きだ。
一見、「間違い」のように見える行動が大正解だったりする。
僕がこの話を知ったのは、池谷裕二さんの著書『単純な脳、複雑な「私」』という脳科学についての本を読んだとき。
実は、僕らの脳にもひねくれアリのような「ゆらぎ」が存在するらしい。
(制限がなくてもまっったく同じ動作をすることが不可能なことがイメージに近いのかも)

全く同じ動きはできない
ゆらぎのおかげで、僕ら人類は何度も試行をすることで、徐々に最適解に近づいていく。
仮にゆらぎがまったくないと、偶然見つけた「正解」を信じ続けて、そのあとの解を見つけることができなくなってしまう。
アリや人間に備わっている「ゆらぎ」はバグでもエラーでもなく、進化する過程で必要な機能なのだ。
「ゆらぎ」がもたらす人間らしさ
当たり前だけど、僕らは機械とは違う。
機械は、疲れないし、文句も言わないし、全く同じ動作だってできる。
人は機械の急激な発達とともに、「人間らしさ」をより好むようになったと感じる。
AIが僕が欲している最適な商品を提案してくれるのも嬉しいけど、僕は好きな人からのプレゼントの方が嬉しい。
それが多少、使いにくかったり、美味しくなかったりしても。
人間は完璧ではないから進化してきた。
人間はダメで、欠点があって、失敗するからイケてるのだ。
ただ、僕らはつい「正解」を求めてしまう。
誰かが見つけた「正解」。
社会が作り上げた「正解」。
でもそれらは最初に見つかっただけかもしれない。
もっとベターな解があるかもしれない。
真っ直ぐに走るのではなく、少し不真面目にひねくれて、寄り道してみる。
「間違い」が「正解」に転じることもあるのだから。